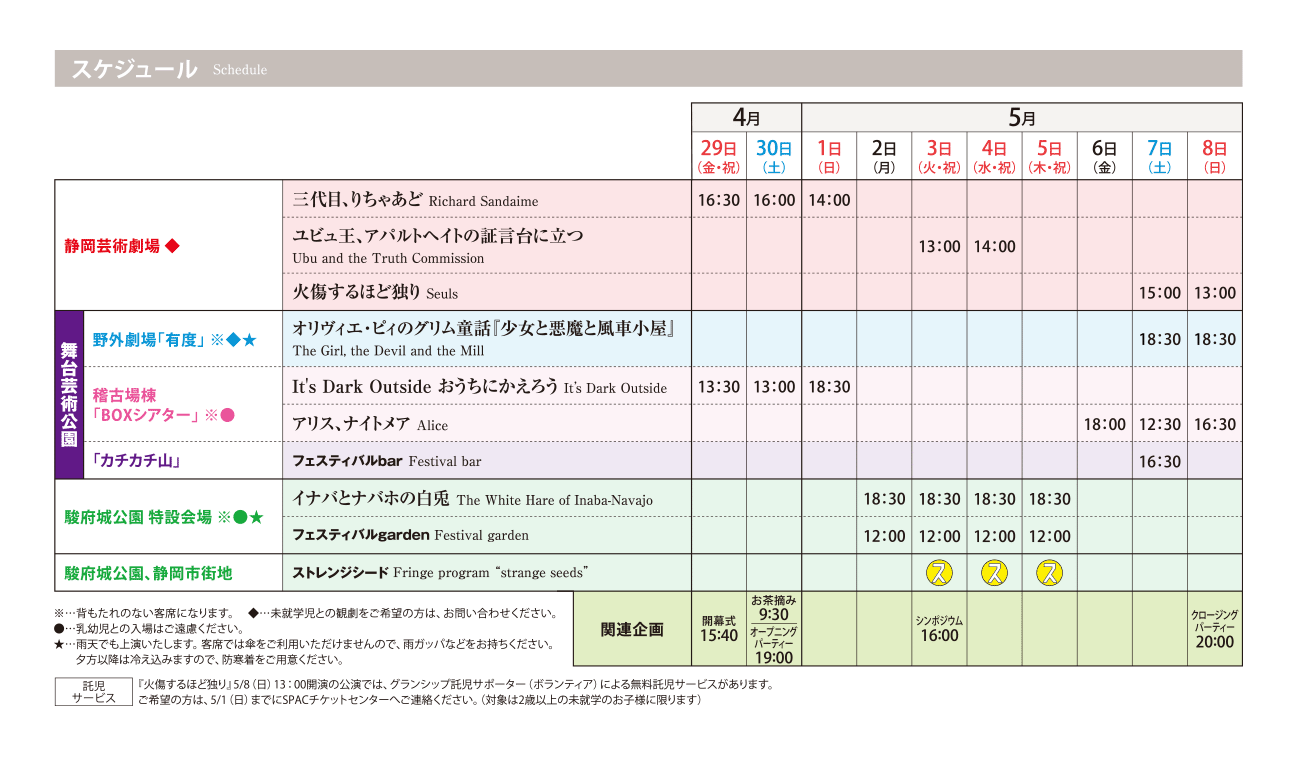アリス、ナイトメア
© Tanya TRABOULSI
Program Information
| ジャンル/国名 | 演劇/レバノン |
|---|---|
| 公演日時 | 5/6(金)18:00、5/7(土)12:30、5/8(日)16:30 |
| 会場 | 舞台芸術公園 稽古場棟「BOXシアター」(全席自由) |
| 上演時間 | 60分 |
| 上演言語 | アラビア語上演/日本語字幕 |
| 作・演出・出演 | サウサン・ブーハーレド |
作品について
眠れない夜の不安、果てしなく増幅する妄想、濃密な演劇空間――。
つぎつぎと彼女を襲う、三本目の足、グロテスクな皮膚、怪物、やせ衰えた猫…。眠れない夜に抱くとめどない不安は、自らの想像力によってさまざまな「不気味なもの」へと拡張していく――!妄想に抗いながら安息を求めてもがく心の奥からの叫びを、一人芝居の濃密な演劇空間の中に描き出す作品。それは内戦のために常に死と隣り合わせの恐怖にさらされ、未来への確信をもてない立場にいる中東・レバノンという土地と、その息苦しい状況下で創作活動をする表現者たちを象徴している。本作は、自らもその一人である作者が直面する葛藤の具現化なのかもしれない。
ベッドひとつの舞台装置に驚きの仕掛け。「中東の演劇の現在」を示す注目作。
演出を手掛けるサウサン・ブーハーレドは、「ふじのくに⇄せかい演劇祭2015」で『ベイルートでゴドーを待ちながら』を上演したレバノンの演劇人イサム・ブーハーレドの妹である。俳優・劇作家でもあるサウサンが、2013年にカイロとベイルートで初演した本作は、舞台にぽつんと置かれたベッド一台だけの簡素な舞台装置が、さまざまな仕掛けとプロジェクターによる映像の効果を借りて変容してゆく。眠りを妨げる憂いの象徴としての禍々しい恐怖と、癒やしの象徴としての母なるものとの間を、さまよいながら膨らみ続ける主人公の夢想を描き出す。
あらすじ
ベッドでキュウリパックをした後、アイマスクをして眠ろうとする一人の女性。なかなか寝付けずにいると、自分のものではない三本目の足に触れたような気がして驚くが、実際には何も見えない。重く圧し掛かる悩ましさを打ち消そうと、子どものころの写真を見ながら母のふとんの温かさを思い出すが、溢れ出る妄想は、化け物、胎児、猫、とかたちを変えて、とどまることを知らない。やがてベッドの下からは、とんでもないものが現れて――。
演出家プロフィール

サウサン・ブーハーレド Sawsan BOU KHALED
俳優・演出家・劇作家。1976年レバノン生まれ、ベイルート在住。国立レバノン大学舞台芸術学院を卒業後、兄イサーム・ブーハーレドの作品などに出演し、演劇活動をはじめる。美術家フセイン・バイドゥーンとの共同作業もこの時期からはじまっている。2000年に渡仏し、パリ第三大学演劇科等で学ぶ。06年、ベイルートで内戦の記憶を扱った最初のソロ作品『クリプトビオシス(休眠状態)』を発表。彼女の作品はエジプト、シリア、ヨルダン、アルジェリア、チュニジア、フランス、ドイツ、ベルギーなどで上演されている。
トーク・関連企画など
◎各回、開演25分前よりプレトークを開催
◎5/6(金)、終演後にアーティストトークを開催
出演者/スタッフ
作・演出・出演:サウサン・ブーハーレド
舞台美術・アニメーション映像制作:フセイン・バイドゥーン
照明:サルマド・ルイ
照明操作: アフメド・ハーフェズ
音楽:『話の話』(ユーリ・ノルシュテイン監督、1979年)のためにミハイル・メェイローヴィッチ(ロシア)がつけた曲
構成:モウリース・ルーカ
協力・後援:アラブ芸術文化財団(AFAC)、レバノン大使館
<SPACスタッフ>
舞台監督:守山真利恵
照明:小早川洋也、板谷航
音響:牧大介、清水慧
ワードローブ:大岡舞、川合玲子
字幕翻訳:鵜戸聡
字幕操作:柳谷あゆみ
通訳:渡辺真帆
制作:熊倉美聡、計見葵
技術監督:村松厚志
照明統括:樋口正幸
音響統括:加藤久直
支援:平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

寄稿
わからない「わたし」と「あなた」のためのアラブ演劇
鵜戸聡
この十年ちょっとだろうか、さまざまな形でアラブ演劇に関するイベントがそれなりに開催されるようになってきたのは。機会を得て東京や静岡でいくつかの催しに参加した折にいろんな言葉を耳にしたが、もっとも印象に残っているのが「難しい」という一言だ。この「難しい」にはいろんなニュアンスがこもっている。たとえば、作品の背景にある社会状況が日本と違いすぎて「難しい」、宗教的な対立が絡んでいるので提示された問題を解決するのが「難しい」、あまりに悲惨な内容なので何と言ってよいのか判断が「難しい」、あるいは、作品自体が何を言いたいのかはっきりしないのが「難しい」、等等。
上演やワークショップ、レクチャーなどの機会に、日本の演劇ファンたちは「真剣に」参加してくれることが多い。あるいは演劇そのものではなく、アラブの文化に興味のある人もたくさんいる。しかし、総じてみんな「真剣」だ。あるいは「深刻」と言ってもいいかもしれない。確かに、パレスチナやイラク、シリアの現状は悲惨と言うべきものだろう。しかし、アラブの演劇家たちは悲劇を伝えに日本までやってくるわけではなくて、悲惨さを越える希望を信じて演劇に何かしらを賭けているはずではないのだろうか。
とはいえ、そう簡単に「希望」が見えてくるほど現実が甘くないのも確かである。ただ、確実に言えるのは、演劇は現実を具体的に確かめ、自分自身への理解を深めるための方法として生きられているということだ。たとえば、レバノンを代表する演劇家で来日経験も多いラビア・ムルエは、内戦で傷ついた身体をいかにして舞台上に再現するか考えた結果、逆にその表象不可能性を暴き立てる作品を次々に生み出すことになった。特定の政治的立場からの「物語」は解体され、肉体と声は分離され、記憶と認識は疑問に付される。そういった否定の操作は、「人間」の否定ではなく、人間を型にはめてしまう自動化した思考の否定なのである。
内戦のように「深刻」な内容にもかかわらずユーモアにあふれた作品が多いのも、思考の硬直を笑いによって揺るがそうとするからだろう。もちろん現地の政治情勢に逐一あてはめながら作品を分析する必要なんて無いのだから、観劇のための予備知識は最低限で十分だ。それに、中東情勢に関しては、中途半端な知識を持っている方が間違った先入観を払拭できないことが多いようにも思える。たとえば、スンナ派とシーア派という、最近はニュースでもおなじみのキーワードで何でもぶった斬ってしまうのがここのところ流行っているようだが、それこそ現実を単純な図式に押し込んで思考を停止させるものと言えよう。アラブ演劇の「難しさ」を敬して遠ざけるのではなく、素直に作品を楽しむことこそが最善の中東理解の方法かもしれない。
さて、今回上演される『アリス』だが、実はレバノンの具体的な事情はまったく出てこない。強いて言えば「キュウリ・パックなんて古臭い美容法がまだレバノンでは現役なのか」と疑問に思うくらいだろうか。しかも、このキュウリこそが本作中でほとんど唯一確かな存在なのだ… こんなことを言われてもわけがわからないだろうが、実際わけのわからない作品である。もう少し言うと、「わからなさ」自体が問題となっているようだ。
前回来日した『ベイルートでゴドーを待ちながら』もそうだったが、暗闇にぼおっと浮かび上がる人影となんだかよくわからないセリフに圧倒される。『ゴドー』はブラックユーモアにあふれた不条理漫才だったが、『アリス』はもう少しストレートに「ホラー」である。『エクソシスト』とか『リング』を彷彿とさせるヴィジュアルで、「アリス」というより「貞子」みたいな女がなんだか狂ったセリフを連ねていく(あるいはヤン・シュヴァンクマイエルの『アリス』か)。ベッドの下に潜んでいる「怪物」を恐れてベッドの上から降りない「わたし」は、もうひとりの「わたし」である「想像上のともだち」と語り合う。別の時間の「わたし」、可能世界の(別でありえただろう)「わたし」が妄想され、「わたし」のさまざまな可能性が示唆されることによって、いまここにいる「わたし」の同一性はだんだん弱められていく。
「わたし」を確かめるには、確実に思われる身体を確かめることから始めるほかない。だが、肉体の構成部分を加算していっただけで「わたし」が成立する訳ではないだろう。むしろ「わたし」の身体の「アリス的」に変幻自在なイメージ(上演をお楽しみに!)は、「わたし」の内に潜む恐るべき他者性をあらわしているのかもしれない。そんな「わたし」自身の「わからなさ」(あるいは「わたし」がわからないこと)が醸し出すえも言われぬホラーは多分にカフカ的だけれども、これもあんまり真面目に見るよりも時にはクスりと笑ってみるのがいいのかもしれない。
≪筆者プロフィール≫
鵜戸 聡 UDO Satoshi
鹿児島大学法文学部准教授。アラブ=ベルベル文学・演劇専攻。共著に『シリア・レバノンを知るための64章』、翻訳にラビァ・ムルエ「これがすべてエイプリルフールだったなら、とナンシーは」(『舞台芸術』第12号』)など。