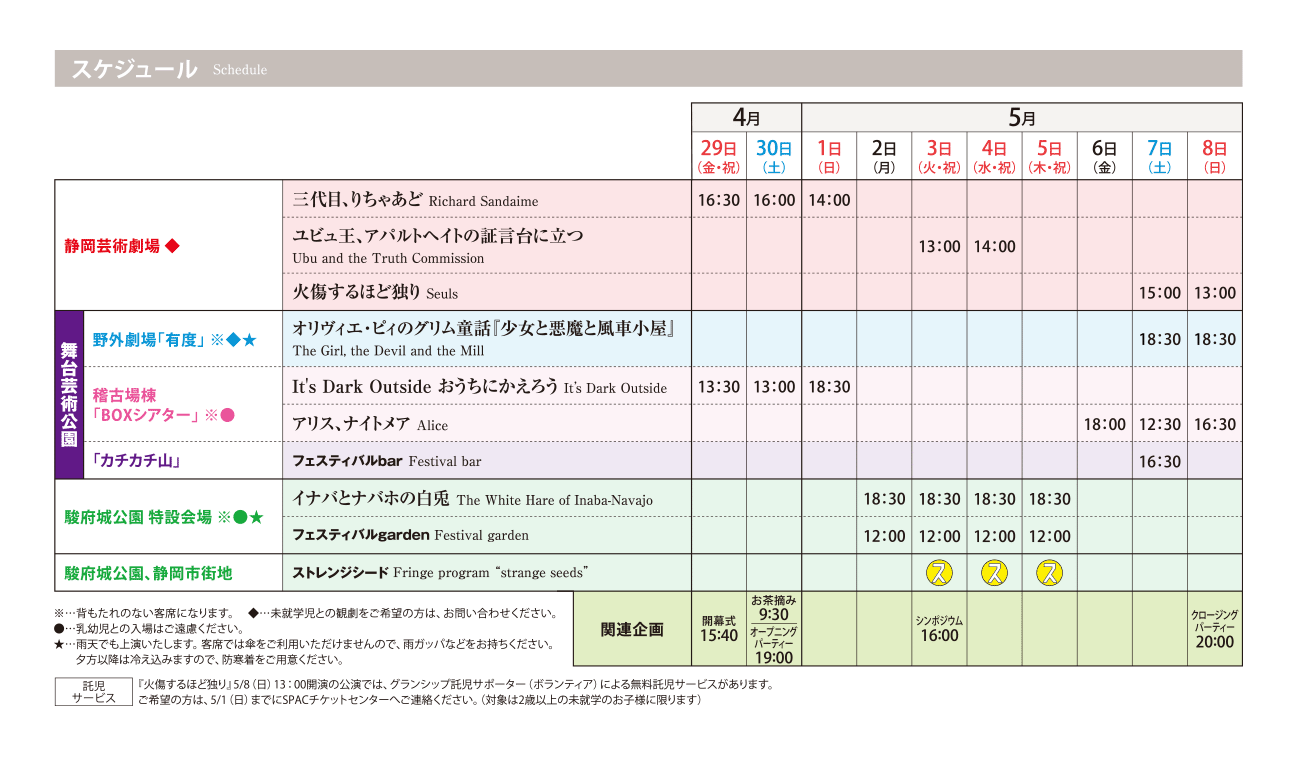三代目、りちゃあど
Program Information
| ジャンル/国名 | 演劇/日本、シンガポール、インドネシア |
|---|---|
| 公演日時 | 4/29(金・祝) 16:30、4/30(土) 16:00、5/1(日) 14:00 |
| 会場 | 静岡芸術劇場(全席指定) |
| 上演時間 | 150分(予定) |
| 上演言語/字幕 | 日本語、英語、インドネシア語上演/日本語、英語字幕 |
| 演出 | オン・ケンセン |
現在、動画コンテンツ準備中です。
作品について
最強の組合せによる「かつてないシェイクスピア」が実現!
舞台は法廷、被告は「りちゃあど」、対する検事は「シェイクスピア」!世界規模で演劇界を揺るがす野田秀樹が『リチャード三世』を潤色し、1990年夢の遊眠社で上演した『三代目、りちゃあど』。シェイクスピアは、リチャード三世らをどうして徹底した悪人として描いたのか――という疑問から生まれたこの戯曲に、シンガポールの演出家オン・ケンセンが最強の布陣で挑む。歌舞伎の中村壱太郎、狂言の茂山童司、宝塚出身の久世星佳、劇団毛皮族の江本純子をはじめ、日本・シンガポール・インドネシアの実力派俳優たち、さらにバリの影絵芝居俳優も参加。残忍・狡猾なリチャード三世を描いた重厚な作品を自由な発想で解体し、知的なドタバタ劇として再構築した野田秀樹の傑作が、アジアのエネルギーを結集して生まれ変わる!
異文化が並び煌めく オン・ケンセンの紡ぐ極彩色アジアンタペストリー
衝撃的な内容で大きな反響を呼んだ『キリング・フィールドを越えて』(ふじのくに⇄せかい演劇祭2012)に続いて2度目のSPAC登場となる、アジアを代表するとともに世界の注目を集める演出家オン・ケンセン。伝統と現代の融合や芸術家同士の国際的な交流に情熱を捧げてきた彼ならではの演出手法は、様々な舞台芸術のフィールドを大胆に横断する。時代/国境、男性/女性、人間/人形、デジタル/アナログ… 相対するものが重なり合う混沌の中に浮かび上がる、アジアの現代が描くシェイクスピア。今秋からはシンガポール芸術祭での上演や日本国内でのツアーも予定されている本作、ここ静岡で誕生する瞬間を見逃すな!
あらすじ
残虐な王・リチャード三世の最後の戦場になったボズワースの天幕。この終幕の舞台は突然に、りちゃあどの罪の有無を争う法廷の場面に変わる。殺人の罪はりちゃあどではなく作者・シェイクスピアにあると主張する弁護士は、実は『ベニスの商人』の悪者としておなじみのシャイロック。彼が弁護を買って出たのは、登場人物を悪人として描いた作者・シェイクスピアに対する復讐のためだった。王位を狙うリチャード三世の物語は華道界の跡目争いに置き換わる。悪から抜け出そうとするりちゃあど、さらなる悪心を吹き込むシェイクスピア…。 作者と登場人物の確執は、一体どこへ向かうのか――?
演出家プロフィール

オン・ケンセン ONG Keng Sen
シンガポール国際芸術祭のディレクター。舞台演出家として現代芸術におけるアジアの美の発展とトランス・グローバリゼーションに積極的に貢献してきた。ニューヨーク大学大学院のティッシュ・スクール・オブ・ジ・アーツのコースを終了した他、法律の学位も持つ。彼のシェイクスピア三部作は、リンカーン・センター、エディンバラ国際フェスティバル、パリ市立劇場、SPAC-静岡県舞台劇術センター、シアターコクーン等、世界各地で上演された。劇団シアターワークスの芸術監督として世界的に有名なフライング・サーカス・プロジェクト(現在休止中)やアーツ・ネットワーク・アジアを立ち上げ、新進のアーティストの指導も積極的に行っている。2001年から03年にかけて開催されたベルリンのイントランジット・フェスティバルを創設した。10年にはアジアのコンテンポラリー・パフォーマンスの功績に対し名誉ある福岡アジア文化賞(芸術・文化賞)を授与された。
出演者プロフィール

中村 壱太郎 (なかむら・かずたろう)
1990年8月3日生まれ。1991年11月京都・南座〈三代目中村鴈治郎襲名披露興行〉『廓文章』の藤屋手代で初お目見得。1995年1月大阪・中座〈五代目中村翫雀・三代目中村扇雀襲名披露興行〉 『嫗山姥』の一子公時で初代中村壱太郎を名のり初舞台。2007年に史上最年少の16歳で大曲『鏡獅子』を踊る。2010年3月に『曽根崎心中』のお初という大役に役柄と同じ19歳で挑む。現在、女方を中心に歌舞伎の舞台に精進しつつ、ラジオやテレビにおける歌舞伎の紹介番組のナビゲーターとしても活動の場を広げている。2014年9月日本舞踊において吾妻徳陽として吾妻流七代目家元を襲名。

茂山 童司 (しげやま・どうじ)
大蔵流狂言方。1983年4月2日生まれ。茂山あきらの長男。父および祖父二世茂山千之丞に師事。1986年、『魔法使いの弟子』(NOHO(能方)劇団)で初舞台。1997年『千歳』、2004年『三番三』、2006年『釣狐』を披く。語学に堪能で近年はNHKテレビの語学番組「プレキソ英語」に“カウドージ”なるキャラクターでレギュラー出演していたほか、国内外でバイリンガル狂言公演や他ジャンルのアーティストのコラボレーションを行うなど表現者としての新境地を切り開いている。2013年夏に自らが作・演出を手掛けるコント公演「ヒャクマンベン」、2014年春に100年後の古典を目指す新作狂言の会「新作“純”狂言集マリコウジ」の両プロジェクトを始動させる。横浜トリエンナーレ2014の正式招待プログラムである「釜ヶ崎芸術大学」の講師として狂言を指導し、新作狂言上演の成功を導く。2015年東京芸術劇場、金沢歌劇座で上演のオペレッタ「メリーウィドウ」の脚本・演出を手掛けるなど役者としてだけではなく演出家としても精力的に活動中。

久世 星佳 (くぜ・せいか)
1983年宝塚歌劇団に入団し、96年より月組トップスターに就任。97年の退団後は、舞台を中心に映画やTVドラマなど多方面で活躍。『OUT』で第8回読売演劇大賞優秀女優賞受賞。映画は『おろち』、ドラマは『第2楽章』『あさきゆめみし~八百屋お七異聞』『警視庁捜査一課9係season9』『金田一少年の事件簿N(neo)』『科捜研の女』などに出演。近年の主な出演舞台に『OUT』『9days Queen~九日間の女王~』『ブレスオブ ライフ~女の肖像~』がある。

江本 純子 (えもと・じゅんこ)
劇作家、演出家、俳優。1978年生。劇団「毛皮族」主宰。2009年『セクシードライバー』、2010年『小さな恋のエロジー』が岸田國士戯曲賞最終候補にノミネート。最近の演出作に『幕末太陽傳』、『ライチ☆光クラブ』(古屋兎丸原作)、『じゃじゃ馬ならし』、作・演出作に『売るものがある性』、『人生2ねんせい』、出演作に『農業少女』(作:野田秀樹、演出:松尾スズキ/東京芸術劇場シアターイースト)、『ふくすけ』(作・演出:松尾スズキ/シアターコクーン)等。

たきいみき
大阪府出身。文楽好きが高じて女優を志す。2001年劇団「ク・ナウカ」入団、06年よりSPAC在籍。宮城聰演出『黒蜥蜴』、『メフィストと呼ばれた男』、『ふたりの女 平成版 ふたりの面妖があなたに絡む』(作:唐十郎)、『夜叉ヶ池』、『真夏の夜の夢』(潤色:野田秀樹)等にメインキャストとして出演。クロード・レジ演出『室内』ほか、フレデリック・フィスバック、オマール・ポラス、ユディ・タジュディンら海外からの招聘演出家の作品でも印象的な役を演じている。

イ・カデック・ブディ・スティアワン I Kadek Budi Setiawan
影絵マスターの家系に生まれる。影絵制作、影絵使い、音楽家、舞踊家としての才能は、共に著名な影絵師であった両親から受け継いだ。5年間ウダヤナ大学で英文学を学んだ後、2010年国立芸術学院(ISI)デンパサール校に進み影絵学科を主席で卒業。影絵師以外にも舞踊家、音楽家としての才能を生かし、日本、イタリア、ドイツ、オーストリア、オランダ、オーストラリアなど世界各国を訪れている。海外での主な活動に、オーストラリア人との共同制作によるバリの伝統的な物語『シータ姫の誘拐』を脚色した影絵芝居(ピーター・ウィルソン演出)、オランダ・アムステルダムのミュージック・ヘボウ・アアン・ヘット・アイでのジャズ音楽と影絵のコラボレーション、13年バリ・アート・フェスティバルでのアメリカのジェン・バンダ演出による影絵芝居『ヴェローナの二紳士 』への出演などがある。

ヤヤン・C・ヌール Jajang C Noer
現在のインドネシアの演劇界と映画界において、演出家・監督・俳優として最も多くの作品に関わっているインドネシア人の女優の一人。『ビビール・メル』で1992年度インドネシア映画祭助演女優賞を受賞した後も、多くの映画で異彩を放ち続けている。他にも2013年東京国際映画祭で上映された『目隠し』、14年にインドネシア映画祭で最優秀作品賞を受賞した『カハヤ・ダリ・ティムール:ベタ・マルク』(14年)などがある。舞台での活躍は72年のティアター・ケトジルとの共同制作に遡る。テレビ映画では『ブカン・ペレムプアン・ビアサ』でイネドネシア・テレビドラマ・フェスティバル最優秀連続ドラマ賞受賞。大女優としてだけでなく、キャストの能力を最大限に引き出す演出家としても知られる。50本近くの映画やテレビ映画に出演しており、インドネシアだけでなく海外でも数々の賞を受賞している。

ジャニス・コー Janice Koh
シンガポールの舞台とテレビで活躍し尊敬を集める俳優であり、任命議員も務めたことがある。シンガポール国立大学で演劇学を学んだ後、ロンドンのゴールドスミス・カレッジでシアター・アドミニストレーションを学び修士号を取得。2003年デヴィッド・オーバーン『プルーフ/証明』の演技により、ライフ!シアター・アワードの最優秀女優賞を受賞。10年にはチャンネル5の法廷ドラマ『ザ・ピュープル』の演技でアジア・テレビジョン・アワードにノミネートされた。海外ツアーにも参加しヨーロッパやアジアの主要な劇場やフェスティバルの舞台にも立っている。主な海外公演として、劇団ワイルド・ライス『アナザー・カントリー 』クアラルンプール公演(15年)、やブリュッセルで開催されたクンステン・フェスティバル・デザールでの『リア王プロジェクト』(08年)、エディンバラ国際演劇祭にもシアター・ワークス『ディアスポラ』(09年)で参加している。
関連企画
『三代目、りちゃあど』出演 茂山童司による「狂言事始め 笑いのワークショップ」
| 日付 | 4月3日(日)13:30~17:00 |
|---|---|
| 会場 | 静岡県舞台芸術公園 稽古場棟 |
| 講師 | 茂山童司 |
| ワークショップ内容 |
1)レクチャー「狂言とは」 2)狂言の基本的な所作を学ぶ 3)あなたも狂言作者、かんたんな狂言を作ってみよう! |
| 参加費 | 1,500円(一般)1,000円(高校生)*参加者保険料含む |
| 対象 | 高校生以上 |
| 定員 | 20名 |
| お申し込み |
受付開始:3月5日(土)10:00 お申し込み先:SPACチケットセンター(TEL.054-202-3399)※お電話/窓口のみでの受付となります。 |
トーク
◎各回、開演25分前よりプレトークを開催
◎4/29(金・祝)、終演後にアーティストトークを開催
出演者/スタッフ
作:野田秀樹
演出:オン・ケンセン
出演:
中村壱太郎:リチャード三世/りちゃあど
茂山童司:シェイクスピア/ジョージ
ジャニス・コー:マーチャン/シャイロク
ヤヤン・C・ヌール:ハハバイ(シェイクスピアの母)/家元夫人
イ・カデック・ブディ・スティアワン:チャボーズ/影絵人形遣い
江本純子:カイロプラクティック/シンリー
たきいみき:ワルカツマー(シェイクスピアの妻)/アン
久世星佳:裁判長/チチデヨカ(シェイクスピアの父)/家元/ワスレガタミ
美術:加藤ちか
照明:スコット・ジェリンスキー
衣裳:矢内原充志
映像:高橋啓祐
音楽:山中透
ヘアメイク:中村兼也
演出補:リサ・ポーター
音響:細越泰良
ドラマターグ:角田美知代
プロダクションマネージャー:大平久美
舞台監督:ザック・ケネディ、山貫理恵
舞台監督助手:川上大二郎、酒井聡澄
照明助手:新島啓介(東京芸術劇場)
衣裳助手:垣根千晶、河ノ剛史、樋口昌美、安食真、稲毛礼子
映像助手:革崎文
通訳:角田美知代、門田美和、金森小百合
パペットデザイン・製作:イ・カデック・ブディ・スティアワン、ジャンティ・プシュパニンシ
大道具製作:株式会社村上舞台機構、株式会社東広
CADオペレーション:QR8C
照明プログラム・操作:吉枝康幸、藤田隆広、柴田晴香(東京芸術劇場)
音響操作:山畑真人、大橋正幸
ワードローブ:阿部朱美
音楽協力:石川智久
衣裳協力:藤井製帽株式会社、WATANABE PILE
台本翻訳協力(英語):ロバート・ティアニー、角田美知代
台本翻訳(インドネシア語):安齋恭子
字幕作成:ザック・ケネディ、斎藤努、黒田忍
字幕:中野一幸(アルゴン社)
稽古サポート:泉陽二
方言指導:前田こうしん
プロデューサー:(東京芸術劇場)高萩宏、宮村恵子、阿部晃久
(シンガポール国際芸術祭)テイ・トン、フレッド・フルムバーグ
制作アシスタント: 斎藤努
<SPACスタッフ>
舞台監督:内野彰子
舞台:降矢一美
照明:樋口正幸
音響:加藤久直、山﨑智美
ワードローブ:大岡舞
技術監督:村松厚志
照明統括:樋口正幸
音響統括:加藤久直
制作:中野三希子、鶴野喬子、梶谷智
芸術局長:成島洋子
主催:SPAC‐静岡県舞台芸術センター
共催:東京芸術劇場、シンガポール国際芸術祭
企画制作:SPAC‐静岡県舞台芸術センター、シンガポール国際芸術祭、東京芸術劇場、熊本県立劇場、吹田市文化会館メイシアター、高知県立美術館、福岡市文化芸術振興財団
助成:一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会、一般財団法人地域創造、平成28年度文化庁国際芸術交流支援事業
協力:松竹株式会社 NODA・MAP、バリ・プルナティ・アート・センター、四国学院大学、株式会社K Productions、株式会社マグナックス、イルミカ東京、小田桐秀一
日・シンガポール外交関係樹立五十周年記念事業
寄稿
『三代目、りちゃあど』をめぐって ―― 近過去を再訪する
内野 儀
シンガポールの演出家オン・ケンセンが野田秀樹の『三代目、りちゃあど』を上演すると聞いて、一瞬、自分の耳を疑った。『三代目、りちゃあど』は、バブル経済崩壊直前の1990年、夢の遊眠社時代に初演されたシェイクスピアの改作劇で、野田の遊眠社時代の代表作のひとつであり、いわゆる80年代小劇場演劇の典型的な作品である。一方、ケンセンは、欧米にとどまらず、アジアでも多彩な活動を展開し、グローバルな芸術的演劇の先端を常に走り続け、現在はシンガポール国際芸術祭の総合監督でもある。88年に初来日を果たし、97年の大規模な『リア』(岸田理生台本)上演以後、大きな作品を日本で上演していないが、若手アーティストとの関係は着実に作りつづけてきた。他方、野田秀樹は、「都市に祝祭はいらない」(平田オリザ)と90年代になって宣言されてからも、NODA・MAPへとその上演主体を変更しつつ、スターシステムに依拠する部分がないとはいえないものの、国内的な人気(=観客動員)は依然として高く、また、英語圏を中心に国際的な活動も行っている。つまり、日本特殊な文脈から登場してきた当時の野田秀樹の初期作品を、シンガポール特殊というよりグローバルな〈芸術としての演劇〉という文脈にその活動初期からいるケンセンが演出することの意味が、わたしにはよくわからなかったのだ。しかも、近年の政治性が比較的直截に表現された戯曲ではなく、一部の観客を除いて忘れ去られたかもしれないかつての作品を取りあげたことが、にわかには了解できなかったのである。
今回の上演のチラシ等に書かれているように、本作はシェイクスピアの『リチャード三世』の改作劇であり、裁判という枠組みを持ち込んで、『ヴェニスの商人』のシャイロックどころかシェイクスピア自身まで登場させてしまう。勝手に妄想の世界を展開する劇作家シェイクスピアの犠牲者としての登場人物たちによる〈逆襲〉がメインのプロットを形成するが、〈逆襲〉される劇作家には長崎出身の野田自身の姿もかなり投影されている。いずれにせよ、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代にふさわしく、西洋文明(=シェイクスピア)など、なんぼのもんじゃい!という気概すら感じられ、その後、「静かな劇」へと沈潜していく演劇史を知るわたしたちにとっては、もしかしたら忘れてしまいたかった「多幸症の時代」の産物ともいえるテクストである。言葉遊びや時空の唐突な移動等のテクストの速度感は尋常ではないものの、言葉は上滑りし(当時よく使われた表現でなら「表層を疾走し」)、原作の持つ悪や権力の問題への深い思索は、触れられはするがすぐにやり過ごされてしまう〈薄い〉テクストである。
ちょうど来日中のケンセンと話す機会があり、そのあたりを少し聞いてみた。彼によれば、これは近年彼が考えている「アジアにおける近代の再訪」というプロジェクトの一環としてある、というのだ。つまり、西洋における近代はルネッサンス以降長く続き、ポスト近代(=グローバル化)になった今、批判あるいは相対化の対象にしかならない。それに比して、それぞれの時間には差異はあるものの、アジアの各地域において主として20世紀以降に成立した近代は、あっという間に過ぎ去りつつあり、グローバル化(=ポストモダニティ)に晒されている。そのときアジアでは100年単位の大過去としての伝統が呼び出されることがあっても、10年、20年、あるいは50年といった短いスパンでの近過去は忘却されているだけではないのか。近過去のある時点に芸術的係留点を見いだすことが、アーティストとしての現在的プロジェクトだとケンセンはいうのだ。もちろんそれは、過去に戻るとかそのままやるとか、そういう意味ではない。同時代的(=現在的)な視座からその近過去の係留点との関係を見いだすことである。そこで選ばれたのが、420年以上も前に書かれた『リチャード三世』を26年前に大きく書き換えた『三代目、りちゃあど』だったというわけだ。
その背後にあるのは、プログラムノートでケンセンが書くように、日本には、特異な多様性/多数性がある、という彼の問題意識である。そしてそれは、アジアという地理的文脈とは切っても切り離せないわけで、今回の上演に、歌舞伎や狂言の役者、宝塚出身や小劇場系の俳優に加えて、シンガポールやインドネシアのアーティストが参加するのは、そういう意味である。こうした異なるパフォーマンスないしは演技の伝統にいる俳優たちが、バブルの真っ最中に書かれた、しかも西洋の伝統をないがしろにする〈薄い〉テクストをどう身体化するのか、あるいはあの速度感とどう対峙するのか、注目している。そこでは、内在的にはなかなか描きだせない〈日本のリアル〉が、もしかしたらノイジーに現象させられるかもしれないからだ。ケンセンには、そうするだけの演出家としての力量があると、わたしは考えているのである。
≪筆者プロフィール≫
内野 儀 UCHINO Tadashi
1957年京都生れ。東京大学教授(表象文化論)。専門は日米現代演劇、パフォーマンス研究。著書に『メロドラマの逆襲』(1996)、『メロドラマからパフォーマンスへ』(2001)、『トランスナショナルな移動性へ』(近刊)等。
寄稿2
オン・ケンセンと『三代目、りちゃあど』
横山義志(SPAC文芸部)
今年2月から3月にかけてフィリピン、インドネシア、マレーシアと東南アジア三カ国を回っていたが、そのときに重宝したのが、この『三代目、りちゃあど』だった。自己紹介のために「ふじのくに⇄せかい演劇祭」のチラシを見せると、はじめは反応が薄いが、『りちゃあど』のところでオン・ケンセンの顔を見つけると、「お、オン・ケンセンと作品を作るのか!おお、ヤヤン・ヌールも出るのか!」と、急に一目置かれるようになる。2014年からシンガポール国際芸術祭の芸術監督をしていることもあるが、それで有名になったというよりも、むしろシンガポールのナショナル・アーツ・カウンシルがオン・ケンセンの絶大な知名度もあてにして依頼したといったところだろう。ヨーロッパでもアメリカ大陸でも、東南アジア出身でこれほど知られている演出家は他に見当たらない。
それは日本でも同様で、オン・ケンセンはとりわけ6カ国から出演者を集め、7カ国で上演された『リア』(岸田理生作、1997年初演)以来、毎年のように来日している。この作品には能楽師で静岡文化芸術大学教授でもある梅若猶彦さんも出演なさっていて、梅若さんを主演にした『夢見るリア』(2012年初演)はニューヨークやパリでも上演された。2012年の「ふじのくに⇄せかい演劇祭」では『キリング・フィールドを越えて』(2001年初演)を上演。クメール・ルージュによる虐殺を生き延びた(「10分の1世代」といわれる)カンボジアの王立舞踊団のダンサーたちが、ポル・ポト時代の長い沈黙のあと、次代に自らの芸を伝えていく様子を、その当事者たちに演じてもらうドキュメンタリー演劇だった。主演のエン・ティアイさんは当時80歳。これを楕円堂で見られたことは、本当に忘れがたい経験だった。
『キリング・フィールドを越えて』
もう一つ、パリの国立ダンスセンターで見た『牛乳の大海のほとりに座ってそれを飲み干そうとする猫のように』(2006)も記憶に残る作品だった。暗闇のなかに、ブノワ・ラシャンブル(カナダの俳優で演出家)の筋骨隆々たる背中が浮かび上がってくる。『ラーマーヤナ』で描かれている洞窟のなかでの猿神と悪魔との戦いが、強烈な身体性と官能的な息づかいをもって語られていく。
『牛乳の大海のほとりに座ってそれを飲み干そうとする猫のように』
ケンセンがアジアの演劇界をリードする演出家になった背景の一つには、リチャード・シェクナー(1934~)との出会いがあるだろう。ケンセンは1993年にニューヨーク大学修士課程に留学し、シェクナーが開設したばかりのパフォーマンス・スタディーズ科で学んだ。シェクナーは「パフォーマンス・グループ」(「ウースター・グループ」の前身)を率いる演出家としても知られていて、ヨーロッパ中心の演劇観とは異なる演劇をつくるために、世界各地の伝統芸能や儀礼の研究を進めていた。2月にマニラでフィリピン文化センター(フィリピンを代表する国立劇場)の芸術監督クリス・ミリヤードにお会いしたが、彼はシェクナー門下でケンセンの一年後輩にあたる。クリス・ミリヤードは「わざわざアメリカまで行って、ニューヨークのユダヤ人から、うちの近所のバリ島の伝統芸能について教えられたんだよ」と笑いながら話していた。
『三代目、りちゃあど』の稽古がバリ島ではじまったのには、20世紀演劇史から見れば、こんな文脈がある。フランスの演出家アントナン・アルトー(1896-1948)がバリの演劇に触発されて「残酷演劇」を提唱し、それがシェクナーに影響を与え、さらにシンガポールの演出家がその影響下で、いわば(広い意味では)「地元」の芸能文化を素材にして作品をつくっていくことになったわけだ。
オン・ケンセンの凄味は、その信じられないようなフットワークの軽さと、強烈な眼力にある。ヨーロッパでもアジアでも日本でも、ふと気がつくとケンセンがいて、大きな背を丸めて「ハロー!」と近寄ってくる。そして面白い人を見つければ、何人だろうがつかまえて、いつの間にか自分のペースにのせてしまう。こういう演出家が、自国だけでは何も完結しえないシンガポールという国から出たのも、ある種の必然のような気もする。
ケンセンが各地の伝統芸能に惹かれたのは、そもそも1965年に独立したシンガポールには「伝統」と呼べるものが少ないからだろう。演劇祭の記者会見で宮城さんが「ケンセンさんはもはや母国語という神話から逃れているというか、母国語という強迫観念からも逃れ、自由になって作品を上演されようとしている。そのことに驚きと刺激を受けます」と話していたが、シンガポールの公用語は英語、マレー語、中国語、タミル語の四つで、英語を母語とする方も多い。この多文化主義こそがシンガポールの「伝統」だともいえるかも知れない。
今年はシェイクスピア没後400年にあたる。今回上演される野田秀樹作『三代目、りちゃあど』では、『リチャード三世』を悪人として描いたシェイクスピアが裁かれることになる。昨年開設された「シンガポール国際商事裁判所」を想起させる設定。シンガポールがアジア経済のハブとしての地位を確立するために、シンガポールとは直接関係のない二国間・多国間の取引も扱うことができる裁判所をつくったわけだが、それ以前から、シンガポールは国際的な取引仲裁の実績を積んできている。シンガポールの国民的歌手ディック・リーのヒット曲『マッド・チャイナマン』(1989)はこんな歌詞だった。「マッド・チャイナマンは自分の人生の東側も西側もあてにしている。(それでも)マッド・チャイナマンはどちらが正しいのか見極めようとする。」アジア各国から選び抜かれた俳優とともに、西と東のあいだ、北と南のあいだをどう裁いていくのか。静岡芸術劇場での初日が楽しみだ。
≪筆者プロフィール≫
横山 義志 YOKOYAMA Yoshiji
1977年生。フランスで演劇学を学んだ後、2007年からSPACで働き、2009年から文芸部で主に海外招聘プログラムを担当。学習院大学等で非常勤講師も。演劇学博士(パリ第10大学)、専門は西洋演技理論史。