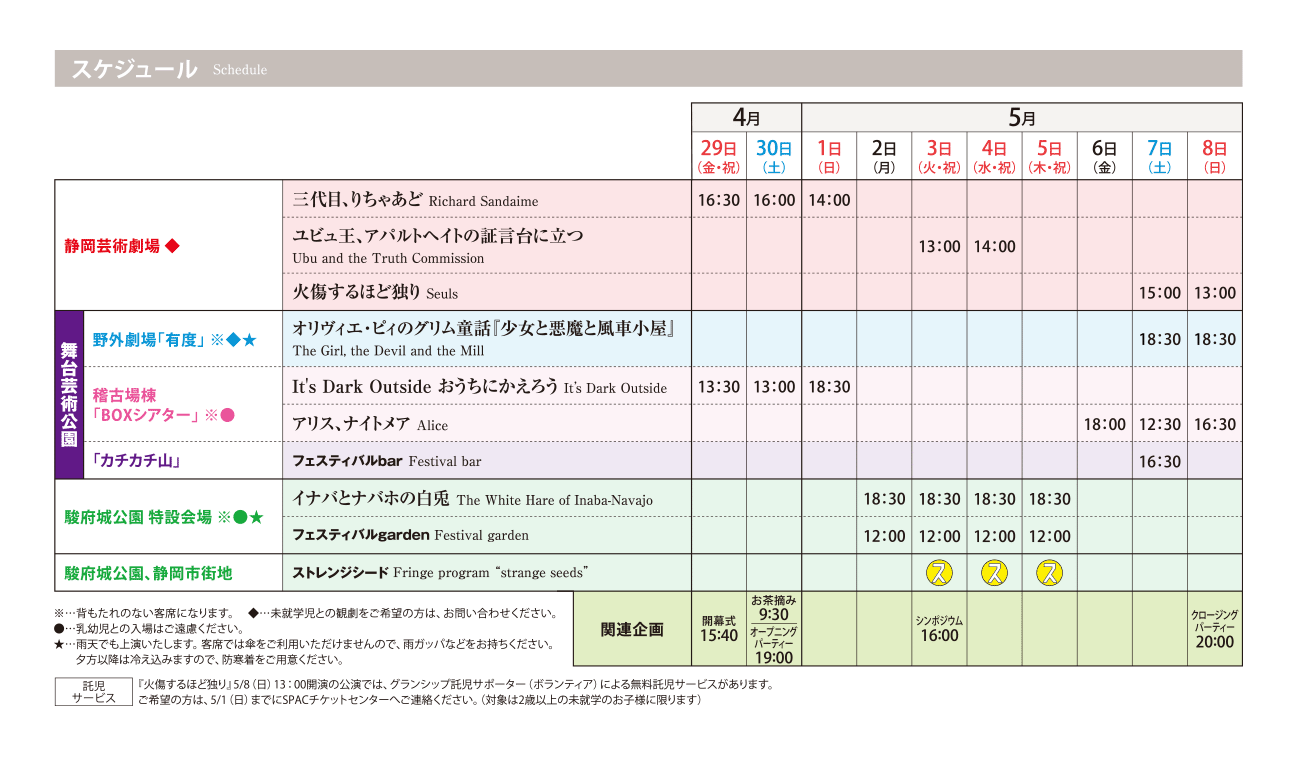『少女と悪魔と風車小屋』
© Christophe RAYNAUD DE LAGE / Festival d’Avignon
Program Information
| ジャンル/国名 | 演劇/フランス |
|---|---|
| 公演日時 | 5/7(土)18:30、5/8(日)18:30 |
| 会場 | 舞台芸術公園 野外劇場「有度」(全席自由) |
| 上演時間 | 60分 |
| 上演言語/字幕 | フランス語上演/日本語字幕 |
| 作・演出 | オリヴィエ・ピィ |
作品について
絶望と再生の物語。アヴィニョンで絶賛の新バージョン、待望の日本初演
世界の演劇シーンの中で最も重要な演出家の一人であるオリヴィエ・ピィ。彼が『少女と悪魔と風車小屋』を2009年にSPACで上演し、世代を超え、国境を越えて人々に深い感動をもたらしたことは記憶に新しいが、なんとこの作品が、2014年のアヴィニョン演劇祭で初演された新バージョンで野外劇場「有度」に登場する。日本平の森に響くノスタルジックな演奏と歌声は、まるで異国のサーカス小屋のよう。悪魔とは知らずに謎の人物と契約を交わしてしまった男とその娘の悲劇が、グリム童話の持つ魅惑的なおどろおどろしさと優しさが入り混じった、不思議な感覚で描かれる。そこには「今ここにある世界を奇跡として生きること」というピィの視点が鮮やかに息づいている。
オリヴィエ・ピィの原点と世界観のすべてがここに
オリヴィエ・ピィが一貫して唱え続けているのは、「言葉の力を信じること」。『少女と悪魔と風車小屋』は、そんなピィの世界観を体現した、原点と呼ぶにふさわしい作品。個性豊かで愛すべき登場人物たちが、どこか懐かしいような優しいメロディに詩をのせて、時に陽気に、時に切なく、ありのままの心の内をうたい上げる。めくるめく展開に、いつしか物語のページを夢中になって読みすすめるように、子どもも大人も一緒になって引き込まれる。かけがえのない大切な人を愛するということ。ピィの放つ飾らない純粋なメッセージは、あらゆる世代の心に響き、まるで癒しの魔法のように胸の奥深くまで染み入ることだろう。
あらすじ
風車小屋に住む粉屋は、森で出会った見知らぬ男から「いま風車小屋の裏にあるものを三年後にくれたら、金持ちにしてやろう」と持ちかけられ、契約を交わしてしまう。粉屋はあっという間に大金持ちとなったが、その時、風車小屋の裏にいたのは粉屋の大切な一人娘だった。三年後、美しく成長した娘を奪いに男が現れる。男は悪魔だったのだ。気まぐれな策略により両手を失ってしまった娘は、悲しみに暮れてひとり放浪の旅に出る。娘は再び希望を見出すことができるのだろうか…?
演出家プロフィール

オリヴィエ・ピィ Olivier PY
劇作家、演出家、俳優。1965年、南仏グラース生まれ。87年にパリ国立高等演劇学校(コンセルヴァトワール)に入学、並行してカトリック学院で神学と哲学を学ぶ。95年、アヴィニョン演劇祭で上演時間24時間という異例の作品『常夜灯―果てしない物語』の7日間連続上演を敢行し、一躍脚光を浴びる。98年から2007年までオルレアン国立演劇センターの芸術監督、同年3月から12年までパリ・オデオン座の芸術総監督を務める。13年、アヴィニョン演劇祭のディレクターに就任。SPACではこれまでに『イリュージョン・コミック―舞台は夢』、『若き俳優への手紙』(08年)、「グリム童話」3部作(09年)、「オリヴィエ・ピィの『<完全版>ロミオとジュリエット』」(12年)、ピィ自身によるシャンソンライブ『ミス・ナイフ、オリヴィエ・ピィを歌う』(14年)を上演。現代フランスを代表する劇作家・演出家のひとり。
こどもと一緒に「せかい演劇」を観よう!
小学生以下無料(要予約)
- 俳優の演技を間近で観られる「おやこ席」がございます。(限定40席/要予約/対象児童:3~12歳/お子様おひとりにつき、大人は2名様まで)
- 開演30分前より、野外劇場前広場にてSPAC俳優によるストーリー紹介のパフォーマンスあり。
- 乳幼児をお連れのお客様は、お問い合わせください。
出演者/スタッフ
作・演出:オリヴィエ・ピィ
原作:グリム兄弟
美術・衣裳:ピエール=アンドレ・ヴェーツ
音楽:ステファヌ・リーチ
照明デザイン:ベルトラン・キリ―
舞台監督助手:アントワーヌ・ローラン
照明監督:ジャック・グリスラン
プロデューサー:ジュリー・ボルデ
出演
父親、王子、子ども、第一の骸骨:フランソワ・ミショノー
母親、庭師:レオ・ミュスカ
悪魔、天使、第二の骸骨:バンジャマン・リテール
少女、姫:デリア・セピュルクル・ナティヴィ
製作:アヴィニョン演劇祭、パリ市立劇場
助成:アンスティチュ・フランセ

<SPACスタッフ>
舞台監督:林哲也
舞台:神谷俊貴
照明:小早川洋也、板谷航
音響:原田忍、青木亮介(株式会社アス)、清水慧
ワードローブ:大岡舞、川合玲子
通訳:安藤博文
字幕(翻訳・操作):西尾祥子
制作:髙林利衣、塚本広俊、佐藤亮太
シアタークルー(ボランティア):松浦康政、小溝朱里、河村夏葵
技術監督:村松厚志
照明統括:樋口正幸
音響統括:加藤久直
支援:平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業

寄稿
芸術と娯楽 オリヴィエ・ピィ『少女と悪魔と風車小屋』について
横山義志(SPAC文芸部)
『少女と悪魔と風車小屋』は、一言でいえば、「奇跡とは何か」という話だ。この世界は悲惨で溢れている。なのになぜ人は希望を持てるのか。他の人を愛したり、美しいものについて語ったりできるのか。それはこの世界そのものが奇跡だからだ。ピィはこの作品で、そんなことを言おうとしているように思える。ピィの作品は長くて難解なものが多いが、子ども向けに書かれたこの作品では、ピィが考えていること、信じていることがすごく素直に表現されているような気がする。
とはいえ、一度見たり読んだりしただけではよく分からないことも多い。ここ三年、学習院大学でのフランス語の授業で、このテクストを学生たちとリーディング・カフェ形式で読んできたが、毎回新たな発見があった。
たとえば、はじめよく分からなかったのは、「余興」の場面がもつ意味。ヒロインの少女は王様と結ばれたものの、王様は戦争に行ってしまう。一人残された王妃のもとに、庭師が骸骨に扮した二人の役者を連れてきて、「あなたの気を紛らせるために余興をやります」という。一見すると、物語の筋とは全く関係がない。グリム童話の原作にも、こんな場面は出てこない。だが、パスカル『パンセ』の話を思い出してみると、これが意外と重要な意味を持っていることに気づかされる。
「気を紛らせる」という言葉は、フランス語で「ディヴェルティール」という。名詞形の「ディヴェルティスマン」は「娯楽」を意味し、英語の「エンターテインメント」の訳語としても使われたりする。『パンセ』には、まさにこの「ディヴェルティスマン」、「気を紛らすこと」を主題にした有名な断章がある。
なぜ貴族たちがウサギ狩りに夢中になるのか。それはウサギが食べたいからではない。それは「気を紛らせ」たいからだ、とパスカルは言う。人はなかなか自分の部屋でじっとしていることができない。それは自分を、自分の運命を見つめてしまうのが怖いからだ。たぶん、つい携帯の画面を眺めてしまうのも。
どんな人にも共通している運命がある。やはり『パンセ』の「人間は考える葦」だという断章では、人間が「自分はいずれ死ぬ」ということを知っているということが、人間というものの尊さを示しているとされている。なのに人は、あるいはだからこそ、ふだんはなるべくそのことを考えないようにして暮らしている。考えてしまうと、恐ろしくて、あるいは空しくて、何もできなくなってしまうかも知れない。
王妃ははじめ「骸骨なんて怖そう」などといって断るが、結局「余興」をやってもらうことに。とぼけた寸劇を見せられて、王妃は「お金をやって返して、私はディヴェルティスマンなんかなくても待っていられます」というが、ふたたび呼び戻し、「あなたたちはアーティストなの?芸術って何?」と骸骨たちに問いかける。すると骸骨たちは「歓びを伴った死です」と答える。
芸術とは、死に向かう生を、歓びをもって生きること。庭師は「花は散るから美しい」と歌う。生きるものの美しさは、やがて死に至る有限性から生まれる。とすれば、芸術と娯楽のちがいは「死を思え【ルビ:メメント・モリ】」という姿勢があるか否か、ということになるのかも知れない。
「神は与え、そして奪う」という言葉で終わる、あの恐ろしいお話を知っているでしょう?、と少女の母親は、悪魔と契約してしまった父親に尋ねる。これは旧約聖書『ヨブ記』の一節だ。敬虔なヨブは、何の落ち度もなかったのに、財産も家族も奪われ、さらには全身をすさまじい皮膚病に覆われることになる。悪魔は神から、ヨブの信仰を試すため、あらゆる災厄を与える許可を得たのだった。この物語はキリスト教神学において「なぜ神がいるのに、この世界には不幸が存在するのか」という問題を考えるうえで重要なものになっていった。『少女と悪魔と風車小屋』はここから多くのモチーフを得ている。
人間の世界には不幸と悲惨が溢れている。なぜ、それでもなお、私たちは世界の美しさについて語ることができるのか。芸術にはそれを「だからこそ」に変える力がある。ピィは演劇とは「受肉の奇跡」そのものだという。言葉が人間に宿って肉をもち、この世界そのもののあり方を変えていく。思えば「死」も言葉に過ぎない。私たちは決してそれを経験することができない。だがその言葉こそが私たちに経験させてくれるものがある。ピィは「信仰よりも奇跡が大事なんだ」とも言う。肉となった言葉を通じて、奇跡が存在していることに気づくこと。演劇にはその力がある、と、ちょっとでも感じてもらえれば、この演劇祭にも意味があったのだろう。
≪筆者プロフィール≫
横山 義志 YOKOYAMA Yoshiji
1977年生。フランスで演劇学を学んだ後、2007年からSPACで働き、2009年から文芸部で主に海外招聘プログラムを担当。学習院大学等で非常勤講師も。演劇学博士(パリ第10大学)、専門は西洋演技理論史。