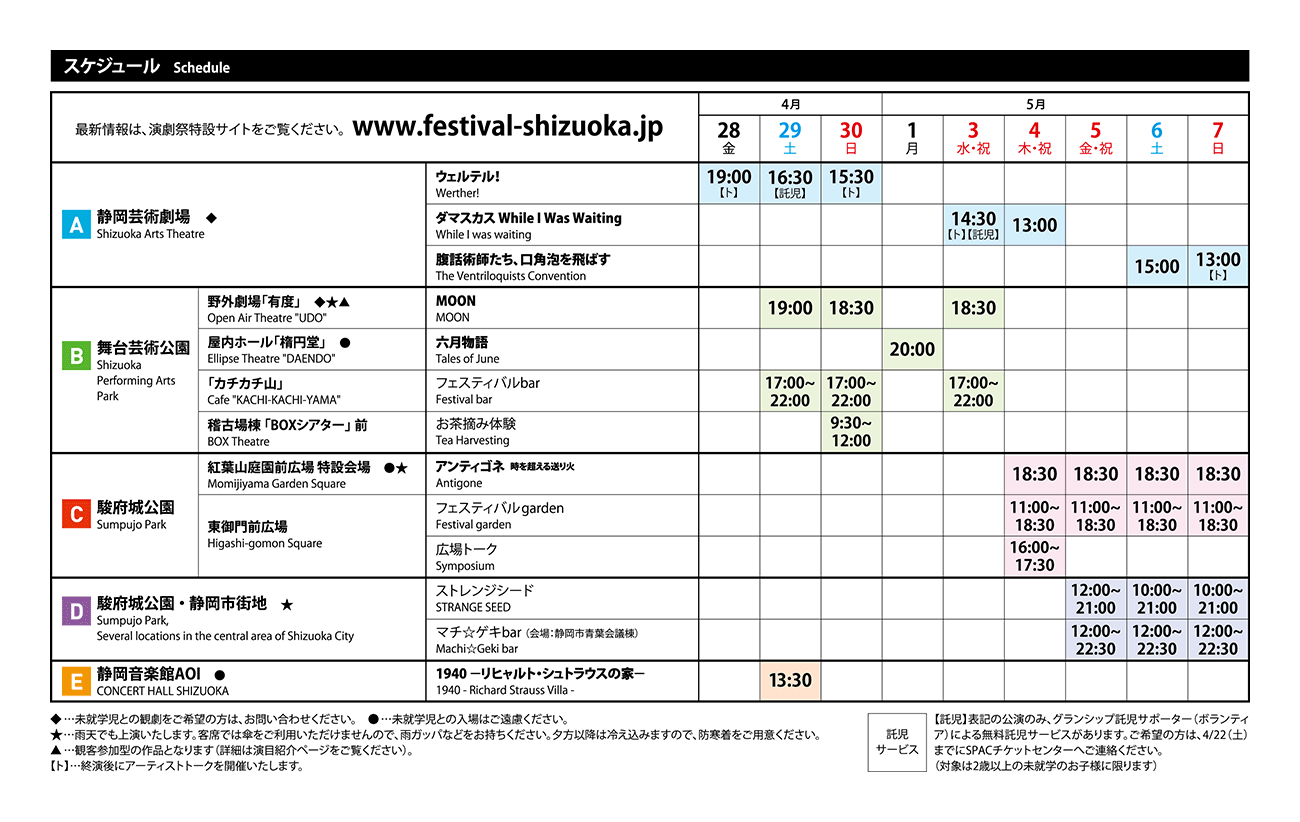アンティゴネ 時を超える送り火
2004年 東京国立博物館 本館前での公演より
© 内田琢麻
Program Information
| ジャンル/国名 | 演劇/日本 |
|---|---|
| 公演日時 |
5/4(木・祝)18:30、5/5(金・祝)18:30、 5/6(土)18:30、5/7(日)18:30 |
| 会場 | 駿府城公園 紅葉山庭園前広場 特設会場 |
| 上演時間 | 未定(120分以内) |
| 上演言語/字幕 | 日本語上演/英語字幕 |
| 座席 | 全席自由 |
| 構成・演出 | 宮城聰 |
第71回アヴィニョン演劇祭オープニング招待作品

アヴィニョン演劇祭メイン会場・アヴィニョン法王庁中庭
このたびSPACは、2014年に続き、世界最高峰の演劇の祭典「アヴィニョン演劇祭」(フランス)に数少ない公式プログラムとして招聘され、宮城聰演出の『アンティゴネ』を同演劇祭のオープニング作品としてメイン会場「法王庁中庭」で上演することが決定しました。アジア圏の劇団が「法王庁中庭」でオープニングを飾るのは、71年の演劇祭の歴史上初めてのことです!
http://www.festival-avignon.com/
公演日:2017年7月6日(木)~12日(水) ※オープニング公演:7月6日(木)
公演数:全6公演(7/6(木)、7(金)、8(土)、10(月)、11(火)、12(水)/ 9日(日)休演)
会場:アヴィニョン法王庁中庭(客席数:約2,000席)
作品について
「演劇の世界遺産」とも言うべき紀元前5世紀の大傑作『アンティゴネ』。
不滅の光を放つ古代ギリシャの“聖火”をいま駿府城公園に灯 す!
古代の悲劇。それは「悲しい劇」ではなく、「人はなぜか必ず死ぬ」という決定的な理不尽を突きつけてくる劇だと言えるだろう。あくせく生きる中で、私たちはいつの間にか死と誕生への畏怖を忘れ、「死ぬ存在」としての人間のいとおしさを忘れてゆく。しかしギリシア悲劇は、この種の鈍感がしまいにはその人を破滅させてしまうのだと喝破し、教訓としてではなく、それを「祭り」として私たちに体験させてくれるのだ。
大空のもと、二千五百年を生きつづけてきた奇跡のせりふを聞き、俳優たちの織りなす音楽に身をゆだねながら命の炎のいとおしさを目の当たりにするとき、閉ざされていた私たちの身体の感覚が奥底から呼び覚まされ、“悲劇こそ生命の賛歌にほかならない”と実感することになる。
没したる者、みな、
いま、世界に向けて発表される、宮城=SPACの新演出!!
他者を「神の側か悪魔の側か」で区分する二分法は、古くから様々な宗教によって流布されてきた。いまや世界中で吹き荒れる憎悪の嵐もそれによって正当化されている。この巨大な裂け目を前に、人間を「味方か敵か」に分けることをしないアンティゴネの思想を、日本人の死生観へとつなげ、今日の世界へ向けた演劇的メッセージを放とうとする壮挙が今回の上演である。生きている間は立場の違いから憎しみ合ったり争ったりするが、死んでしまえばみな等しく仏になれる――。宮城+SPACによる『アンティゴネ』の物語は、誰もが成仏したことを寿ぐ祭り=「盆踊り」へと向かってゆく。
あらすじ
舞台は古代ギリシャ・テーバイ。先の王オイディプスは自らの出生の秘密を知り、国を追われる。その妻であり母でもあるイオカステは自死を遂げた。残された二人の息子ポリュネイケスとエテオクレスは王位を競って争い、ポリュネイケスはアルゴスに追放される。やがてポリュネイケスはアルゴス勢を率いてテーバイに攻め入り、エテオクレスとの一騎打ちとなるが、オイディプスの呪いを受けた兄弟は相討ちとなって共に果てる。そして王位はイオカステの兄クレオンのものとなった。クレオンは国を守ったエテオクレスを手厚く葬り、反逆者ポリュネイケスの死骸を野に晒して野鳥の餌にすることを命じ、これに反した者を死罪に処すことを決める。だが、オイディプス王の娘アンティゴネは王令に従わず、いさめる妹イスメネにも抗して、兄ポリュネイケスに埋葬の礼を施すことを決意する…。
演出ノート
演出ノート
宮城 聰
『アンティゴネ』は、数あるギリシア悲劇の中でも、最も人気の高い作品のひとつです。
なんで人気があるのかなと考えてみると、まず第一に、若い女性が主役だ、ということが挙げられるでしょう。ギリシア悲劇には、若い女性が主役の芝居は案外と少ないんですね。(他には『エレクトラ』くらいでしょうか。)
もうひとつの理由は、「無力な若い娘が、自分の信念に従って、強大な権力を持つ男にまっこうから立ち向かう」という構図でしょう。この対決の構図で、若い娘の側に肩入れしない人は滅多にいないですよね。
そして第三に、これもギリシア悲劇には珍しく、若い男女の純真な恋愛がドラマの大きな柱となっていることを加えるべきかと思います。
つまりは、芝居の「仕立て」が、そもそも観客好きのする条件を備えているということですね。芝居の中で語られる中身よりも、まずは「仕立て」がすばらしい。
では中身の方はどうかというと、こちらは「仕立て」ほどには万人受けするものではありません。もちろん、『アンティゴネ』の中身についても、たくさんの著作がものされ、たくさんの重要な議論が重ねられてきました。ただ、それらは、演劇人がこの戯曲を劇場のプログラムに入れようと考える直接の理由には、あまり、なってこなかったと思います。むしろ、中身を観客に訴えたくて上演する演劇人は、「仕立て」は原作からそのまま借りて、中身は自分たちで新たに書きおろした台本を作り、“新アンティゴネ”として上演してきたと言っていいでしょう。ブレヒトしかり、アヌイしかり…『アンティゴネ』ほど改作の多い古典戯曲は他に見当りません。
しかし今回私たちは、原作のメッセージこそ今の世界の人々に届けるべきものだ、と感じて、『アンティゴネ』を上演することにしたのでした。
昨年の7月、「2017年のアヴィニョン演劇祭に招聘したい」というオファーを受けて、僕らはアヴィニョンに下見に向かいました。フェスティバルの方々が下見の為に用意してくれていた会場は2ヶ所。ひとつは「法王庁中庭」、もうひとつは「聖ヨセフ高校中庭」というところでした。僕自身は、後者では面白い作品をいくつも観た記憶がありますが、法王庁中庭で面白かったと思った経験はほんとうにわずかしかなく、「よっぽど使いにくい空間なんだろうなぁ」という先入観を持って下見に行ったのでした。
しかし、実際に法王庁の中庭に立ってみたら、なんというか、激しくかきたてられるものがあったのです。あの空間が「イメージ喚起力」を持っていたと言いかえても良いのですが、つまりは、「ここで『アンティゴネ』をやるしかない」という確信が突如として僕の心を占めたのです。
なんでそんな考えが突然湧き上がったのか——あとから思い返してみて気づいたのは次のようなことです。
こんにちの世界をしんかんさせている戦争や殺りくは、その多くが、人間を神の側と悪魔の側の2つに分け、神の側の自分たちが悪魔の側の相手を攻撃する、という原理のもとにおこなわれているのではないか。このような戦争は、人間をパッカリと正邪の2種類に分ける思想から生まれるものであって、それはユダヤ教—キリスト教—イスラム教という「砂漠の宗教」が世界に広めていったものではないか? 一方、近代以前の日本には「悪魔」という概念が成立しなかったことからもわかるように(あるいは「魔がさす」という言い方にもあらわれているとおり、)かつての日本人は人間を正邪の物差しで2つに分けることはできないと考えていて、それゆえひとたび死んでしまったら、その人の生前のおこないにかかわらず、すべての死者を「仏」と呼んでいた。このような人間観こそ今日の世界に必要なものではないだろうか?そして、アンティゴネが訴えたことはまさにこのことだと言えるのではないか?
—妙に話が大きくなりましたが、アヴィニョンの法王庁という、かつてすべての力(ちから)がそこに集中していた場と向きあうと、演劇の上演さえも大きな座標軸の上で考えないではいられなくなる、ということだったのだと思います。
アヴィニョン演劇祭の「顔」である法王庁中庭でのオープニング作品を任されるのは、日本では私たちが初めてです。演劇祭側にとっても、日本語の芝居が開幕を飾るというのは大きな賭けで、大英断だったと思います。もう、考えれば考えるほどプレッシャーですが、しかしその『アンティゴネ』を、アヴィニョンでの世界初演に先がけてここ駿府城公園でお披露目できるのは本当に嬉しいことです。どうしたら駿府のお客様に楽しんでもらえるだろうか、と頭をひねっていると、おのずとプレッシャーは霧消し、芝居をつくる喜びが私たちの体を満たしてくるのです。
演出家プロフィール

宮城 聰 MIYAGI Satoshi
1959年東京生まれ。演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京大学で小田島雄志・渡辺守章・日高八郎各師から演劇論を学び、90年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出は国内外から高い評価を得ている。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、また、静岡の青少年に向けた新たな事業を展開し、「世界を見る窓」としての劇場づくりに力を注いでいる。14年7月アヴィニョン演劇祭から招聘されブルボン石切場にて『マハーバーラタ』を上演し絶賛された。その他の代表作に『王女メデイア』『ペール・ギュント』など。04年第3回朝日舞台芸術賞受賞。05年第2回アサヒビール芸術賞受賞。
劇団プロフィール
SPAC-静岡県舞台芸術センター(Shizuoka Performing Arts Center)
専用の劇場や稽古場を拠点として、俳優、舞台技術・制作スタッフが活動を行う日本で初めての公立文化事業集団である。舞台芸術作品の創造と上演とともに、優れた舞台芸術の紹介や舞台芸術家の育成を事業目的として活動している。1997年から初代芸術総監督鈴木忠志のもとで本格的な活動を開始。2007年より宮城聰が芸術総監督に就任し、事業をさらに発展させている。より多彩な舞台芸術作品の創造とともに、「ふじのくに⇄せかい演劇祭」の開催、中高生鑑賞事業や人材育成事業、海外の演劇祭での公演、地域へのアウトリーチ活動などを続けている。13年8月には、全国知事会第6回先進政策創造会議により、静岡県のSPACへの取り組みが「先進政策大賞」に選出された。また14年7月、フランスの世界的演劇祭「アヴィニョン演劇祭」に、『マハーバーラタ~ナラ王の冒険~』と『室内』の二作品が公式プログラムとして招聘され、称賛を浴びた。
トーク
◎プレトーク:各回、開演35分前よりフェスティバルgardenにて
出演者/スタッフ
構成・演出:宮城聰
作:ソポクレス
訳:柳沼重剛
音楽:棚川寛子
空間構成:木津潤平
衣裳デザイン:高橋佳代
照明デザイン:大迫浩二
ヘアメイク:梶田キョウコ
出演:SPAC/美加理、本多麻紀、赤松直美、阿部一徳、石井萠水、泉陽二、大内米治、大高浩一、加藤幸夫、貴島豪、榊原有美、桜内結う、佐藤ゆず、鈴木真理子、大道無門優也、武石守正、舘野百代、寺内亜矢子、永井健二、布施安寿香、牧山祐大、三島景太、宮城嶋遥加、森山冬子、山本実幸、吉植荘一郎、吉見亮、若菜大輔、渡辺敬彦
製作:SPAC-静岡県舞台芸術センター
寄稿
アンティゴネの時
大宮勘一郎
ソフォクレスの悲劇『アンティゴネ』は、古代ギリシャから数多の時空を超えた近代の日本においてもその根源的な力を失うことがない。もちろん、ソフォクレスのこの作品が不朽不滅の名作の一つであるのは間違いないとしても、この作品が私たちの心を特別な仕方でざわつかせるとき、心ざわつく私たちの側にもまた理由がある。現代に生きる私たちにだからこそ、これをその都度決して忘れがたい作品として受け取らずにはいられない事情があるのだと思う。
『アンティゴネ』は「喪」をめぐる劇である。死者を弔うことは、「死すべき存在」たる人間にとって不可欠な、いわば人間を人間たらしめる行為といえようが、この「あたりまえの務め」がアンティゴネを苦しめ追い詰める。その姿からは、一つの問いが浮かび上がるだろう。それは、「喪」は — 「喪」さえもが — 「政治」なのか、という問いである。アルゴスの軍勢は去り、テーバイの独立は護られたが、戦後処理を担う新王クレオンは、祖国の将エテオクレスを手厚く葬らせる一方で、逆賊ポリュネイケスの埋葬を禁じる。戦い相斃れた兄二人を等しく弔うことを当然とするアンティゴネは、王の掟と対立し、ここに悲劇『アンティゴネ』は始まる。
この悲劇について、そしてアンティゴネという存在について、筆者はこれまで何度か考えさせられた。それは必ず、その都度別の理由があってのことだった。アンティゴネは特定の状態に置かれた人間に「考えること」を促すのである。東西対立の終わった1989~90年、阪神で天地が鳴動し東京の地下鉄に毒が撒かれた95年、摩天楼が崩壊した2001年、そして東北の地と海がともに波うち原発事故で多くの生命と故郷が奪われた2011年以降は、何を論じ考えるにもアンティゴネに随き従っているかのようである。それどころか、原発事故のおよそ2ヶ月後、この心をとらえて離さぬ動揺に駆られた筆者は、失礼を顧みず、宮城聰さんに「福島で『アンティゴネ』を上演されませんか?」という無謀極まる提案のメールを突然送りさえした。2004年に宮城さんの演出で上演された『アンティゴネ』の印象が強くよみがえってきたのだった。
一方でアンティゴネは、「父母未生以前」から執拗に続く因果応報の連鎖に絡みとられた存在である。他方しかし彼女は、その連鎖に立ち向かう存在でもある。ただし、クレオンのようにその連鎖を、立法という人間の術策によって断ち切ろうとして破滅するのではない。むしろ彼女は、人がこしらえたのですらない「誰も知らぬほどに古い」喪の掟に従うことで、おのれに絡みつく因果さえも弔おうとするのだ。これは、より古くからの習わしだから、という単に消極的で受動的な従属ではない。アンティゴネはこの古い掟にこそ、因果を超えた倫理を認め、これに従い、そのために王に抗してしまう。王の掟が領民すなわち特定の領域に住む生者のみを拘束する一方で、この古い掟は生者死者の別も領域内外の別も知らない。生者もまた「死すべき存在」であり、領域とは人間の術策の所産にすぎないのだからである。喪の人アンティゴネは、古い掟のこの無差別を体現する。
むろん、「喪もまた政治なのか」という問いに、これだけで「否」と答えたことになるわけではない。クレオンがアンティゴネを生ある者たちの共同体の彼方に放逐するのは、法に従った裁きであるにみえて、実際には「敵は戦死しても敵のまま」という政治の過拡張であり、喪の政治化である。そこでは弔う者もまた「汝は友か、敵か」という政治の問いに晒されるだろう。しかしアンティゴネは、この問いを静かに粉砕する。味方でも敵でもなく、単に愛する人々として死者を弔うのだ、という彼女は、彼女を敵とみなすクレオンたちの行く末を慮りさえする。ここで喪はついに政治から解放されるのだ。そのために自らもこの世を去らねばならぬ彼女に、悲しみはあっても悔いはない。弔う者、ですらなく、弔いそのものとなる彼女は、生きながらえることを、そして同時に政治をもはるかに超えた輝かしい存在である。この美の輝きの前では、王も王の掟も色くすんでしまう。生ある者たちとその「まつりごと」の虚飾は、灰色に沈むのである。
喪の政治化は、生ある領民と領土を排他的に護ろうとする王と国法の僭越である。こうした僭越は、争いの起きるその都度ごとにやまず繰り返される。そして、それが繰り返されるところには、生なきものたちの言葉を語る存在が必ず現れるだろう。アンティゴネは不滅である。それは生なきもの、ないし「死の力」の反復的な作動であり、アンティゴネを突き動かすのもこの「生ける死の力」である。筆者はかつてそれを「アンティゴネ・マシーン」と仮に名付けたことがあり、その拙い文章が宮城さんの目に止まったのだった。
倫理、美、そして機械 — アンティゴネを形づくるこれら3つの要素は不可分に結びついて、死者をさえ友と敵に区別しようとする国法を揺り動かした。それが今では別の形で私たちの心をざわつかせる。機械は鎮まらず、国法は自ずと揺らぎ、逆意のあるなしにかかわらず皆がポリュネイケスの仕打ちを受ける。アンティゴネの美が遠く投げかける暗い影の中に、私たちはいつ頃からか生きているのかもしれない。
再び『アンティゴネ』の時が到来するのだ。
<筆者プロフィール>
大宮 勘一郎 OMIYA Kanichiro
1960年生。東京大学教授。ドイツ文学・ドイツ思想。ベンヤミン、アーレント、ゲーテ、クライストらの研究を行っている。著書に『ベンヤミンの通行路』(未來社)、翻訳にゲーテ「若きヴェルターの悩み」(集英社)など。