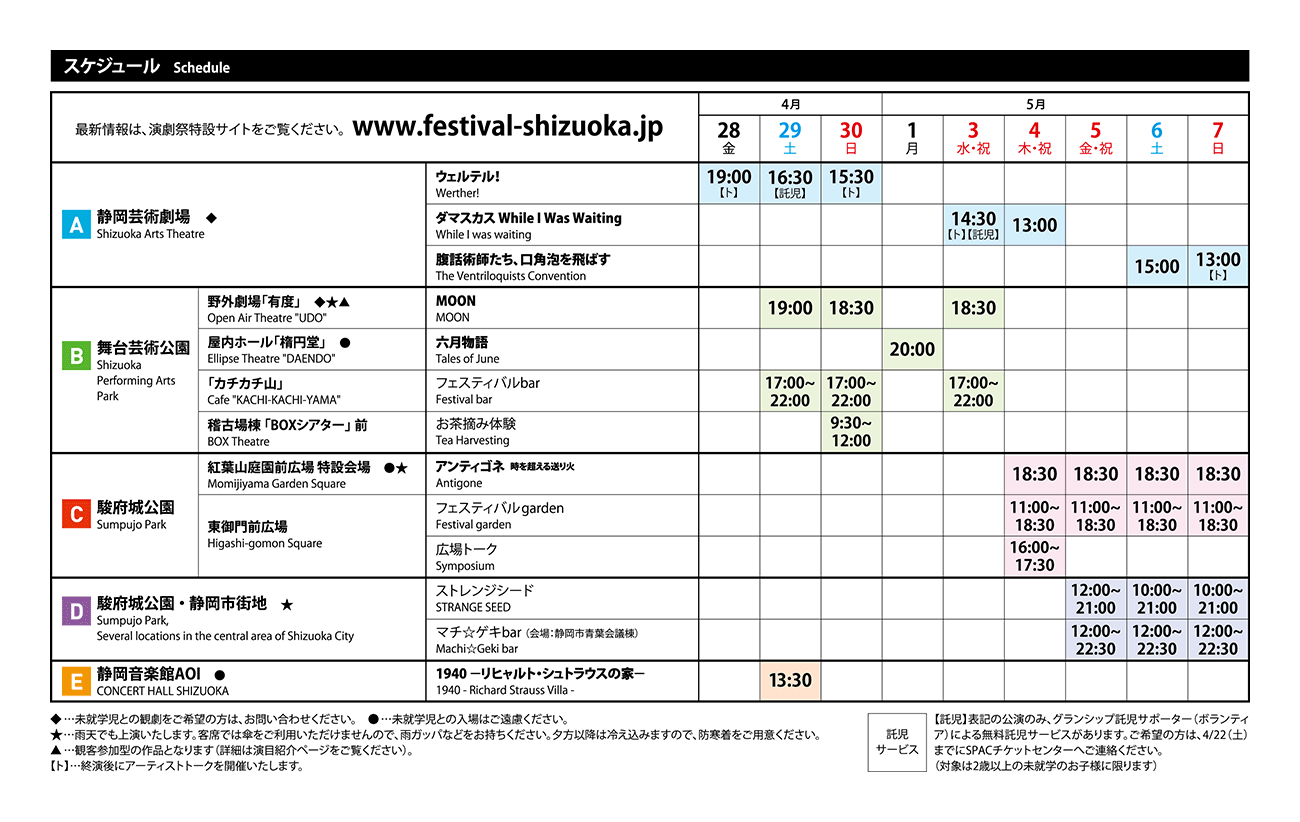六月物語
© Caterina DE BARTOLO
Program Information
| ジャンル/国名 | 演劇/イタリア |
|---|---|
| 公演日時 | 5/1(月)20:00 |
| 会場 | 舞台芸術公園 屋内ホール「楕円堂」 |
| 上演時間 | 90分 |
| 上演言語/字幕 | イタリア語上演/日本語字幕、日本語通訳 |
| 座席 | 全席自由 |
| 構成・演出・出演 | ピッポ・デルボーノ |
作品について
生まれながらのストーリーテラー、ピッポによって世界が語り尽くされる!
むきだしの舞台、あるのはテーブルとイス、一本のビール瓶。研ぎ澄まされた空間で、ピッポ・デルボーノは即興で語りだす。デルボーノ自身の壮絶な人生、そこに挟み込まれる寓話、自由や愛についてのポエム、そしてそれらを抑圧するものへの抵抗の叫び…。語られる断片は個人的なようでいて、言葉が重なり合い紡がれる物語は、まるで空気中に漂う記憶や悲しみと共鳴するかのように膨らみ、誰しもの心をゆさぶる。『戦争』『沈黙』の2作を披露し衝撃を与えた2007年の初来日公演から、待ちに待った日本初演作。1ステージのみの貴重な上演が、静謐な楕円堂の舞台で実現する。
苦闘する人生を一篇の詩へと紡ぎ上げるダイナミズム
ダンスや文学、パレードや儀式までを内包し、日常を舞台へと生まれ変わらせるイリュージョンに満ちたデルボーノのパフォーマンス。本作では、自伝的な語りが普遍の詩へと昇華する。彼曰く、「演劇とは、言葉をみずからの命をこめて読むこと」。愛する人の死、自身の体を蝕む病、人生に次々と訪れる苦難を前に、彼は演劇を求め続けた。舞台上にその身をさらけ出すようにして語られる本作は、「読むこと」で命をつないできたという彼の実感にあふれている。「死」に向き合ってきたデルボーノだからこそ描き出せる、繊細かつ強靭な「生」への讃歌である。
あらすじ
イタリアの小さな村、信仰あつい家にデルボーノは生まれた。教会のクリスマスの催しで幼子キリストを演じたのが最初の演劇体験だった。思春期に薬物を常習する一方で、生への強い希求は彼を演劇へと駆り立てる。恋人の突然の死、孤独、そして自身の病。常に死と隣り合わせに生きる中、ある時、ろうあ者で全盲のボボと出会う。長く精神病棟に入院していた彼を連れ出し、向かった故郷への旅で、二人は新たな世界を発見していく。
演出ノート
演出ノート
ピッポ・デルボーノ
子供の頃のことを思い出す。六月はホタルの月だった。夜になるとホタルが飛んだ。おじいさんと一緒に、長い時間、ただ黙って、満天の星の海に浮かぶホタルを眺めていた。
六月は死と再生の月だった。時が移りゆく月だった。夏が来ようとしていた。私たちは海のそばに住んでいた。いつまでもつづく夕暮れの月だった。私の誕生日の月だった。そして演劇をはじめた月だった。そして恋がはじまった月だった。
そしてまた喪失の月でもあった。嘆きの月。不安の月。
『六月物語』はローマで生まれた。恋愛について、個人的な体験を話してくれ、と言われた。そして、その最初の物語に、いくつもの物語が加わっていった。これは「演劇という選択がなぜ生きていくために必要であったのか」を語る物語なのかもしれない。
私はこの『六月物語』を、いろいろな国で、いろいろな言語で演じてきた。イギリスではロイヤル・シェイクスピア・カンパニーで、フランスではいくつもの劇場で、スペインではいくつものフェスティバルで、ラテンアメリカで、東欧諸国で、ほかにも多くの国々で演じてきた。
「私的(プライベート)なものこそが政治的なのだ」。70年代の新たな運動では、よくこう言われていた。それは変化をもたらす新たな方法だった。権力の嘘に、あなた自身の個人的な真実を対置するのだ。私の物語は、ひとつの人生そのものだとも思ってもらえるだろう。演劇との出会い、恋愛との出会い。そして病気や死との出会い。悲しみ、狂気、自暴自棄、そして再生との出会い。ボボとの、あの聾唖(ろうあ)の小男との、ナポリに近いアヴェルサの精神病施設での出会い。ボボは私にとって、演劇活動・芸術活動の上でも、また私の人生にとっても、欠かすことのできない存在となった。
『六月物語』は講演会のようなものだということもできるだろうが、講演会ともいえず、芝居ともいえず、どちらでもあり、どちらでもない。
なによりもまず、それは人生についての、演劇についての、生き残りをかけた闘いについての物語だ。
さまざまな出会いについて話す。自分の舞台や、自分がこのような演劇をやっていることの意味について話す。だがそれもまた、何か別のものになる。何なのかは分からないが、もしかしたら知りたくないのかもしれないが。
今まで、これを上演するたびに、会場は深い沈黙と集中に包まれた。私にとっては、それこそが演劇なのだ。すべてが宙づりになり、深い沈黙、深い集中だけが残る、あの瞬間。
(翻訳:SPAC文芸部 横山義志)
演出家からのビデオメッセージ
皆様こんにちは。
私は現在トリノで、自分の劇団と「orchids(蘭)」を上演しています。
今回、静岡に再び訪れることになり、とてもうれしく思います。
前回は静岡で、私の劇団と『戦争-Guerra』『沈黙-Il Silenzio』の二つの作品を上演しました。
雨が降る中で上演を続け、観劇してくださったお客さまも、小道具の原稿も雨に濡れたのをよく覚えています。
終演後のトークでも、皆様ずぶ濡れになりながらじっと私を見つめて話を聞いてくださっていました。
この演劇祭は、そういう、本当にすばらしい機会です。
そんな場所に戻ってこられることを、うれしく思います。
今回はぺぺと一緒に行きますが、前回とは違って独りで、語りの芝居(モノローグ)をやります。
このモノローグは、前回の静岡でも出演したボボを含めた色々な人達との出会いや、
病気や死との戦い、その中に見出す幸せ、そして「演劇」そのものをテーマにしています。
この作品をあなた方の演劇祭で上演することが、とても大事なことだと考えています。
では、またすぐお会いしましょう。チャオ!
演出家プロフィール

ピッポ・デルボーノ Pippo DELBONO
演出家、劇作家、俳優。1986 年に自身の劇団を立ち上げ『暗殺者の時』を発表、ヨーロッパや南米を中心に300 回に渡る上演を重ねる。90年には『壁』(90)でピナ・バウシュとのコラボレーションを行なった。97 年、アヴェルサ精神病院で行ったワークショップをもとに、障害者、ホームレスの人々と『浮浪者たち』を制作。以後このメンバーの多くが劇団の一員として活動を続ける。「Shizuoka 春の芸術祭 2007」で上演した『戦争』『沈黙』 をはじめ、アヴィニョン演劇祭、 ウィーン芸術週間、ヴェネツィア・ビエンナーレ等で多数の作品を発表。人間の生を鋭く見つめ、詩的かつ衝撃的に舞台上に描き出し、各地で絶賛を受けている。
出演者/スタッフ
構成・演出・出演:ピッポ・デルボーノ
製作:エミリア=ロマーニャ州演劇財団、ピッポ・デルボーノ・カンパニー
寄稿
ピッホ・デルボーノにおける引用の意味
芦沢みどり
ピッポ・デルボーノが10年ぶりにSPACへやって来る。劇作家/演出家/俳優/ダンサー/映画監督と-多彩な顔を持つこの演劇人は、イタリアで最も型破りで特異なシアターアーチストの一人と言われている。
「特異な(different)」という形容詞は、10年前に静岡芸術劇場と野外劇場「有度」で上演された『戦争―Guerra』と『沈黙―Il Silenzio』を語る時にも使われた。2つの作品はピッポ自身も含めた15人ほどの編成の舞台で、高い身体表現能力とダンス・テクニックを持つパフォーマーたちに混ざって、彼の長年の盟友で聾唖者のボボをはじめ、ダウン症児や障がい者、元ホームレス、ストリート・アーチストらが加わっていた。いや、加わっていたと言うよりむしろ圧倒的存在感を示して舞台の中心にいた。ピッポは彼らを、社会の周縁に生きる生を体現した「特異な」表現者なのだと、あるインタビューで語っている。『戦争―Guerra』は『オデュッセイア』に想を得た作品で、パフォーマーたちはオデュッセウスのように己の生の中心を見失って世界をさまよう。一方の『沈黙―Il Silenzio』は1968年にシチリア島で起きた地震に材を取っており、自然の暴力の前で人は沈黙するほかないが、再生の可能性もある。そのことを明示した舞台だった。
2作とも死と再生を主旋律とするスペクタクル的な舞台で、多様な身体による表現の断片が時空間にコラージュされていた。そこにはいわゆるセリフはないが、言葉が排除されているわけではなく、身振り、表情、ダンス、音楽などの合間に引用の言葉が投げ込まれる。ピッポがマイク片手に舞台に飛び出して来て読み上げるテクストは、チェ・ゲバラやブッダ、パゾリーニやランボーなどからの引用で、それらが挿入されると、眼前の身体表現に歴史の時間が流れ込み、表現の断片が奥行のあるものに変容した。
このたび上演される『六月物語』は、10年前の舞台から一転して、何もない空間でピッポ1人が1時間半を語り通す。それで思い出したのがマイクと原稿を持って舞台をエネルギッシュに走り回っていた大柄で小太りの彼の姿だ。今回はぎりぎりまで舞台の要素をそぎ落とし、たった一人で観客と向き合い、即興で自分語りをするという。子供時代の思い出、演劇を始めるに至った経緯、人との出会い-この語りをピッポはジャズの即興演奏に譬えている。なるほど。身体を楽器に見立てた生演奏ということなら、ちょっとお腹の出た彼の体型だと、幼児にもなれるし老人にもなれるか。間違いなく豊かな音色の、存在感ある楽器になるだろう。
とくに興味深いのは、ここでもテクストの引用が舞台の重要な構成要素であることだ。引用の演劇としてよく知られている作品にベケットの『しあわせな日々』がある。舞台中央の円丘にうもれた初老の女が、引用をちりばめたセリフを長々としゃべるのだが、彼女の引用はいつもウロ覚えで、口にする古典のテクストは現実と切り結ばず、表層的な言葉の遊びに終わってしまう。もちろんこれは古典テクストの深層の意味が失われたことへのパロディーで、ベケット不条理劇の優れた仕掛けではある。戯曲とパフォーマンスの違いはあるにしても、ピッポの引用は、もっと切実で、現実の体験に切り込んで行くものらしい。『六月物語』について、どのように思い出し語り紡いで行くのかを問われて、とりあえず人生のパートナーに出会った時と同じように作家たちとの出会いを思い出しながら語るのだ、と彼は答えている。心の傷や痛み、人としての弱さを舞台上でさらけ出す時、そこに挿入される引用が即興の語りにどのような意味作用をもたらすのか。それを見定めるのも、今回の舞台の見どころかと思う。
日本初演だが、アヴィニョン演劇祭をはじめヨーロッパで数回上演されている。過去の舞台ではベケット、ピナ・バウシュ、シェイクスピア、サラ・ケインなどが引用あるいは言及された。とはいえ、いつも同じとは限らないのが即興の即興たるゆえんだ。これを上演する時はいつも、時間をかけてその土地を散歩し、さまざま吸収して安心してから舞台に立つのだそうだ。六月は自身が生まれた月であり、夏の始まる月であり、蛍の飛び交う月であり、死と再生の月だとピッポは言う。蛍が飛び交う季節にはひと月ほど早いが、1回きりのパフォーマンスをジャズの即興演奏のように楽しむのもいいかもしれない。
<筆者プロフィール>
芦沢みどり ASHIZAWA Midori
現代英米戯曲翻訳家。これまでの舞台上演作品にマーチン・マクドナーの『リーナン三部作』、ニコラス・ライトの『クレシダ』ほか多数。OM2や解体社などパフォーマンス系舞台評を寄稿。