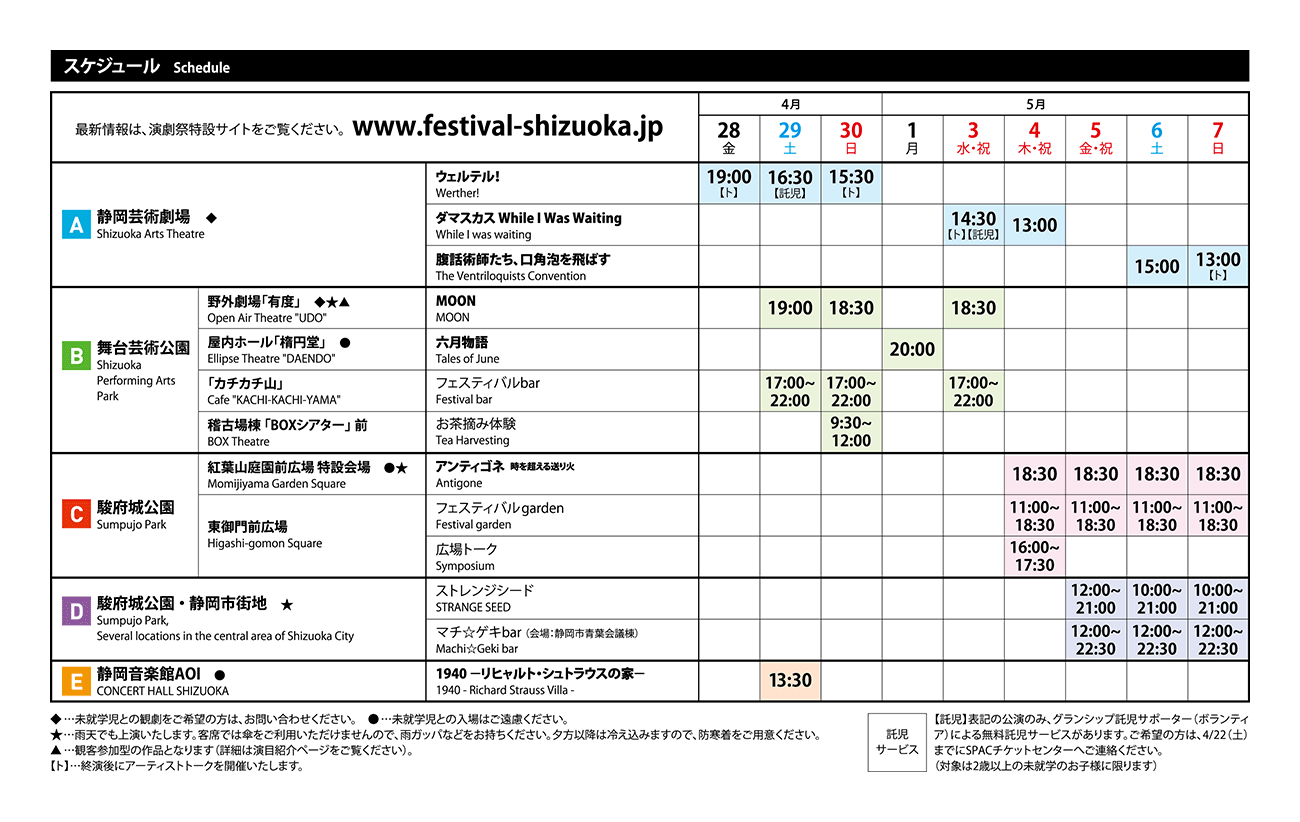ダマスカス While I Was Waiting
© Didier NADEAU
Program Information
| ジャンル/国名 | 演劇/シリア |
|---|---|
| 公演日時 | 5/3(水・祝)14:30、5/4(木・祝)13:00 |
| 会場 | 静岡芸術劇場 |
| 上演時間 | 100分 |
| 上演言語/字幕 | アラビア語上演/日本語字幕 |
| 座席 | 全席自由 |
| 演出 | オマル・アブーサアダ |
作品について
混乱の地に生きつづける人々、その息づかいを間近に聞く
出口の見えない内戦状態が続くシリア。政府側と内部分裂した反政府勢力との戦闘は、IS(通称イスラム国)の台頭や大国の思惑によって一層泥沼化している。その首都、ダマスカスにとどまり活動する演出家と、シリアからの亡命を余儀なくされた劇作家が、議論を重ねこの地に生きる人々の姿をリアルに描いた。ダマスカスの「今」を映像や音を通じて記録しようとする若者とその家族の物語から、複雑きわまる政情の渦中で生活を営む人々の不安と希望を浮き彫りにしていく。昨年5月に発表され、名だたる国際演劇祭で脚光を浴びた話題作が、早くも静岡芸術劇場に登場する。
シリア人自ら描く現地の「リアル」。絶望の中に希望の視点
舞台は、何者かに襲われ昏睡状態に陥った若者が、肉親や見舞客らを2階部分から見下ろす重層的なセットの中で展開する。演じていない役者たちも舞台上に留まり、両脇から成り行きを見つめる。若者の活動を引き継ごうとする者、反発する者、それを見守る者、いずれもシリアに留まり生き続けようとする人々の実像そのもの。役者たちのたたずまいは想像を絶する生々しさを放ち、観客は彼らをとりまく厳しい現実が我々の生きる世界と地続きであると、痛烈に体感することになる。絶望の中にありながら希望にも視点が置かれ、苦闘する人々の迷いと決断が深く胸を打つ。
あらすじ
ダマスカスに住む青年タイームは、民主化運動に身を投じたものの、政府に武器で抵抗する仲間から平和路線を批判される。そんな中、生まれ育った愛すべき街を映像で記録することに自身の使命を見出し始める。だがある日、彼は検問所で何者かに襲撃され、意識不明の重体に——。彼を世話する家族や、見舞う友人、恋人の会話を見つめるタイーム。彼ら一人一人の日常もまた、シリアという国の政治的難局に狂わされていた。
演出ノート
オマル・アブーサアダ インタビュー
※このインタビューは2016年7月アヴィニョン演劇祭での公演のためになされたものです。
―最新作『ダマスカス While I Was Waiting』はどのようにして生まれたのですか?
この企画について考え始めたのは2年前のことでした(※)。親友が殴打されたあと昏睡状態になったのがきっかけでした。その後彼は亡くなりました。その後、友人の医師にこのことを話したら、彼のおかげで、シリア国内のいくつもの病院を訪問して、昏睡状態になっている患者の近親者の方々と話をすることができ、それを記録していきました。ムハンマド・アル=アッタールがそれをもとに台本を書き、稽古しながら台本をふくらませていきました。この作品を通じて、昏睡状態になった人が自分の体と、そして自分の想像力と、どんな関係を結ぶことになるのかを考えてみました。その近親者たちは、昏睡状態になった人々の世話をすることになっただけでなく、戦争によって日々の習慣を変えざるをえなくなっているわけです。この人たちがどうやって日々をやり過ごそうとしているのかを描いてみたいと思いました。また、このような試練に直面して、近親者が心のうちでどのような反応をしているのか、ということにも興味がありました。昏睡状態になった人と向き合うのは、個人的には、死と向き合うことよりも難しいことだと感じられたからです。この作品の登場人物たちはそれぞれ、さまざまな方法で、若い男を目覚めさせようとします。たくさん話す人もいれば、家族の近況を聞かせる人、彼が好きだったもののことを話す人、シリアでの暮らしの大きな変化を話す人、等々。また、ヨーロッパに渡ることを決意する人、シリアにとどまることを選ぶ人など、それぞれの登場人物が選ぶ道も見えてきます。
『ダマスカス』は、私たちの夢を問い直す手段でもあります。2014年に、息子が2010年からずっと昏睡状態になっている、という女性に出会いました。その間に、息子の兄弟姉妹のうち2人は殺され、1人は亡命し、父親は亡くなり、彼の友人たちは去って行ったか、あるいは軍隊に入隊しました。彼女は毎日、もし息子が目覚めたら今の状況についてどう話せばいいものか、と悩んでいました。私が2011年に想像していた2016年は、民主主義社会が到来して、生活水準も向上し、私たちの日々の生活もより自由になる、というものでした。今起きているのは、全く逆のことです…。こんな単純な思いが、この作品に込められています。
―昏睡状態ということは、まだ生きている、希望がある、ということですよね。シリアも同様に昏睡状態にある、とお考えでしょうか?
そうですね。確かにシリアという国は、生きても死んでもいません。でもこのメタファーはいろいろなレベルに適用することができるでしょう。昏睡状態というキーワードから見てみれば、『ダマスカス』に出てくる若者たちは、革命のあいだは活発に活動していましたが、今はもう姿が見えなくなっているか、あるいは状況に影響力を与えることはできなくなり、ただただ今の状況を耐えている、といったところです。革命があってから5年たって、『ダマスカス』はシリアの状況について、また私の演劇活動についても、1つの総括をする機会となりました。革命がはじまったとき、私は熱狂して街に出ていきました。演劇を通じた活動もしていました。ですが5年後の今、私の状況は、5年前に思い描いていたものとは全く異なります。私たちの理想は変わっていないのに、なぜこうなってしまったのか。それを理解しようとすることは大事なことだと思うのです。演劇の仕事をはじめて以来、私は政治性の重要さを訴えてきました。政治的演劇の価値は、まだ目に見えるものにはなっていないが、成果をあげる可能性はあるはずだ、と考えていたのです。
今ではかつてほど単純には考えなくなりました。現政権は新しい社会の出現への唯一の障壁ではない、ということも見えてきました。主要な問題の1つは、シリア社会の根本的構成の問題で、家族制度がどうしても父や宗教といったものに引き寄せられて定義されてしまうという問題なのです。
また、シリアが地域ごとに異なる利害のネットワーク、そして地域の利害を超えた、世界的な利害のネットワークの中にとらわれてしまった、ということも見えてきました。これも大きな問題です。今の私は、「自分の国で社会正義を実現するには、世界規模でそれを追求するほかない」と考える人々に近い考えを持っているように感じています。昏睡状態というテーマを扱ったのは、このような変化に気づいたからでもあります。
「希望」についてのご質問でしたね。私の作品にはいつも希望がありました。希望とは生命そのものであり、生命の成長、生命の歩みそのものなのです。
(編 Francis Cossu/アラビア語シリア方言からの仏訳 Simon Dubois/仏語からの邦訳 SPAC文芸部 横山義志)
演出家からのビデオメッセージ
アブーサアダさんから日本の皆さんへ
実はこの『ダマスカス While I Was Waiting』は、実際に僕の知り合いに起こった出来事から着想したものです。彼はダマスカスで体制側の暴行を受け、意識不明になりその2か月後に亡くなりました。この話に僕は衝撃を受け、戯曲にできないかと考えたのです。それで脚本家のムハンマド・アル=アッタールに話を持っていき、この作品が出来ました。
この作品は2015年ごろのダマスカスを巡る話です。意識不明の青年を軸にその家族や親しい人たちの変化を描いています。そして内戦下、約1年間のダマスカス社会を戯曲という形で表しました。またこの作品は、主人公の青年だけではなく、2011年の反体制運動(「アラブ革命」)において、積極的に活動していた青年たち全般の状況も示しています。「アラブ革命」が多くの死者を出す内戦状態に陥るなか、彼らの活発さは徐々に沈静化し、彼らも事態を見つめるだけで積極的な対応は出来なくなっていきました。
今回、初めて日本で上演することになり、この貴重な経験をとてもうれしく思っています。前から日本の文化に興味がありましたし、日本の映画や演劇も多少知っています。この作品は現在シリアで起こっていることについて、日本の皆さんにいくつもの疑問を投げかけるものになると思います。またネット等で入手できる情報とは異なる、事実の一側面を示すものでもあるでしょう。僕は、演劇は事実のある側面を共有する場であると考えています。
演出家プロフィール

オマル・アブーサアダ Omar ABUSAADA
1977年生まれ。シリア出身の演出家。2001年にダマスカスの演劇学校を卒業後、ドラマトゥルク、演出家として活動を開始する。02年に劇団Studio Theatre を共同で設立し、04年に初演出作『不眠症』を上演。その後『許し-少年刑務所の受刑者との即興劇』(09年)、『シャティーラのアンティゴネ』(14年)などを演出。近年はシリアの伝統と新しい手法を組み合わせた同時代的な脚本や、中東の様々な村の人々との出会いを基にしたドキュメンタリー演劇に取り組んでおり、政治・社会的問題意識に基づいた作品は、数々の国際演劇祭でも紹介されている。現代演劇の劇作・演出ワークショップも活発に行っている。
作家プロフィール
ムハンマド・アル=アッタール Mohammad AL ATTAR
1980年生まれ。シリア出身の劇作家、ドラマトゥルク。ダマスカス大学で英文学を学んだ後、ダマスカスの演劇学校で演劇を学ぶ。2010年にはロンドン大学ゴールドスミス・カレッジで応用演劇の修士号を取得。『撤退』『オンライン』『親密さ』『シャティーラのアンティゴネ』など多くの作品が、ダマスカス、ヨーロッパ主要都市、ニューヨーク、ソウルなどで上演されている。劇作のほかには、雑誌や新聞でシリア蜂起についての記事も数多く執筆しており、アラブ世界で疎外されている人々との演劇を利用したプロジェクトも継続して取り組んでいる。
トーク
◎プレトーク:各回、開演35分前より
◎アーティストトーク:5/3(水・祝)終演後
出演者/スタッフ
演出:オマル・アブーサアダ
作:ムハンマド・アル=アッタール
出演:ムハンマド・アール=ラシー、ナンダ・ムハンマド、ムハンマド・アッ=リファーイー、リハーム・アル=カサール、ハナーン・シャキール、ムスタファ・クル
共同製作: アヴィニョン演劇祭、ナポリ演劇祭、アラブ芸術文化財団(AFAC)、舞台芸術拠点ラ・フリッシュ・ラ・ベル・ド・メ(マルセイユ)、テアター・シュペクターケル(チューリッヒ)、オナシス文化センター(アテネ)、ヴォーライト(ゲント)、ラ・バティ・フェスティバル(ジュネーブ)、レ・バン・ピュブリック=フェスティバル・レ・ランコントル・ア・レシェル(マルセイユ)、フェスティバル・ドートンヌ(パリ)、マルセイユ国立劇場ラ・クリエ、ル・タルマック(パリ)、モンテビデオ(マルセイユ)
寄稿
小さな物語と大きな物語の溝
岡崎弘樹
確かにシリアの芸術家がこぞって2011年の「アラブの春」の訪れを歓迎したわけではない。「革命はエジプトで可能であったとしても、シリアでは不可能」と体制支持を表明する往年の喜劇スターもいた。とはいえ、それまで名の知られていなかった者も含め、人々と共に街区に繰り出し、詩や小説、絵画、風刺画、人形劇、記録映画を通して自由への渇望を表現した芸術家も少なくなかった。シリアの演劇活動家もこの渦中にいた。一般市民への弾圧、そして殺戮の連鎖が広まる中で国外に出ざるを得なかったとしても、彼らはニューヨークやパリ、ドバイ、ベイルート、あるいはヨルダンのザアタリ難民キャンプで、ドラマセラピーも含めた多様な活動を現在まで続けている。今回上演される『ダマスカス While I Was Waiting』の若手演出家のアブーサアダもまた、こうした演劇人の一人だ。
アラブ世界でシリアの劇作家として広く知られているのは、アブーサアダよりも一世代前に属する面々だ。マンドゥーフ・アドワーン(1941~2004)やムハンマド・マーグート(1934~2006)、サアダッラー・ワヌス(1941~1997)に代表される民族主義時代の申し子は、英雄不在の無慈悲な戦争、指導者の無能力、国民的経験としての殉教、パレスチナ解放の挫折、または刑務官と収監者を隔てる厚い壁といった主題を、物語の背景に据えた。いわば政治性を明確に意識した「大きな物語」を前提として虚構を練り上げていた。特にワヌスは、史劇を通じて自分達の遺産や文化から新たな伝統の創造を模索した。アラブの大義への絶望と自殺未遂による10年以上の断筆を経て、パレスチナでの第一次インティファーダの最中で書かれた『陵辱』(1990)では、シオニズムを特徴付ける占領と暴力を、決して隣国に留まらず、アラブの体制にまで浸透している深刻な課題として提起した。
旧世代の影響力は依然として計り知れない。とはいえ今世紀に入り、アブーサアダの言う通り、「シリアの演劇界が新たな聴衆を得るのに失敗していた」のも事実だ。彼はもともと国内で若手演出家として注目され始めていたが、特に脚本家ムハンマド・アッタールと組み、シリア危機の最中に国外に活動拠点を移してから、国際的に注目を集める代表的な演劇人となった。『カメラをのぞき込んでくれ』(2012)では、不当に拘束され過酷な拷問を強いられる若者とそれを映像に収める記録映画監督の物語に取り組んだ。また『シャティーラのアンティゴネー』(2014)では、悲惨な生活状況の代名詞であるベイルートのパレスチナ難民キャンプを題材に、実際に難民生活を送るシリア人とパレスチナ人女性が舞台に立つ。祖国にも亡命先にも見放されるだけでなく、目の前の男性らにも支配され、二重、三重の抑圧下で生き抜かざるを得ない女性像に迫った。
若手コンビは、政治的背景を意識しつつも、日常に埋没する現実の人間やその生活空間、あるいはその日常が崩れていく瞬間に着目する。脚本を執筆する段階で最近釈放されたばかりの者や実際に避難民キャンプに暮らす女性にインタビューを重ね、個人の醜聞レベルの逸話も含め具体的で詳細にわたる「小さな物語」を捉え、虚構を紡ぎ出していく。演出も型にはまったものではない。プロの役者とアマの証言者の共演や、映像を自由自在に用いて記録映画との境目を行き来するような演出は、過去のシリア演劇と比べても極めて斬新だ。
若手コンビがこれまで描こうとしてきたのは、小さな物語と大きな物語の間に横たわる越えがたい溝だ。当作品も然り。自由を叫び街区に繰り出したとしても、自身はいわゆる「反体制派」に属しているわけではない。そもそも政治に関わる気はなく、武器をとるなどもっての他だとしても、親友が拘束されれば、もはや沈黙できず、何らかの応答を迫られる。デモに出れば撃ち殺されるかもしれないという恐怖を克服するには、お馴染みの宗教的なフレーズを口にする場合もある。だが、それがネット上の動画として流れれば「イスラム過激派による政権転覆の試み」というレッテルを貼られる。読み替えられ、分類され、数字化された言説が域内外諸国の政治的思惑と結びつく中で、シリア人は皆が皆、底なしの沼にずるずると引き込まれていく。
生きているわけでもなければ、死んでいるわけでもない。アブーサアダは当作品で混沌とした意識不明の状態にシリアの現状を例えつつも、こう断言する。「演劇が政治的な役割を果たし、抵抗の手段となることが分かった」。演劇が社会を変えるわけではない。だが少なくとも、演じる者や観客を励まし、勇気を与え、問題の本質に向き合い、声を上げ、手を取り合い、新たな文化を創り出す一助になる、と信じる若者だ。
<筆者プロフィール>
岡崎弘樹 OKAZAKI Hiroki
アラブ近代政治・文学思想研究者。元在ダマスカス日本大使館専門調査員。パリ第三大学アラブ研究科で社会学博士号を取得。19世紀末のアラブ演劇に関する研究論文の他、シリア映画での助演歴もある。