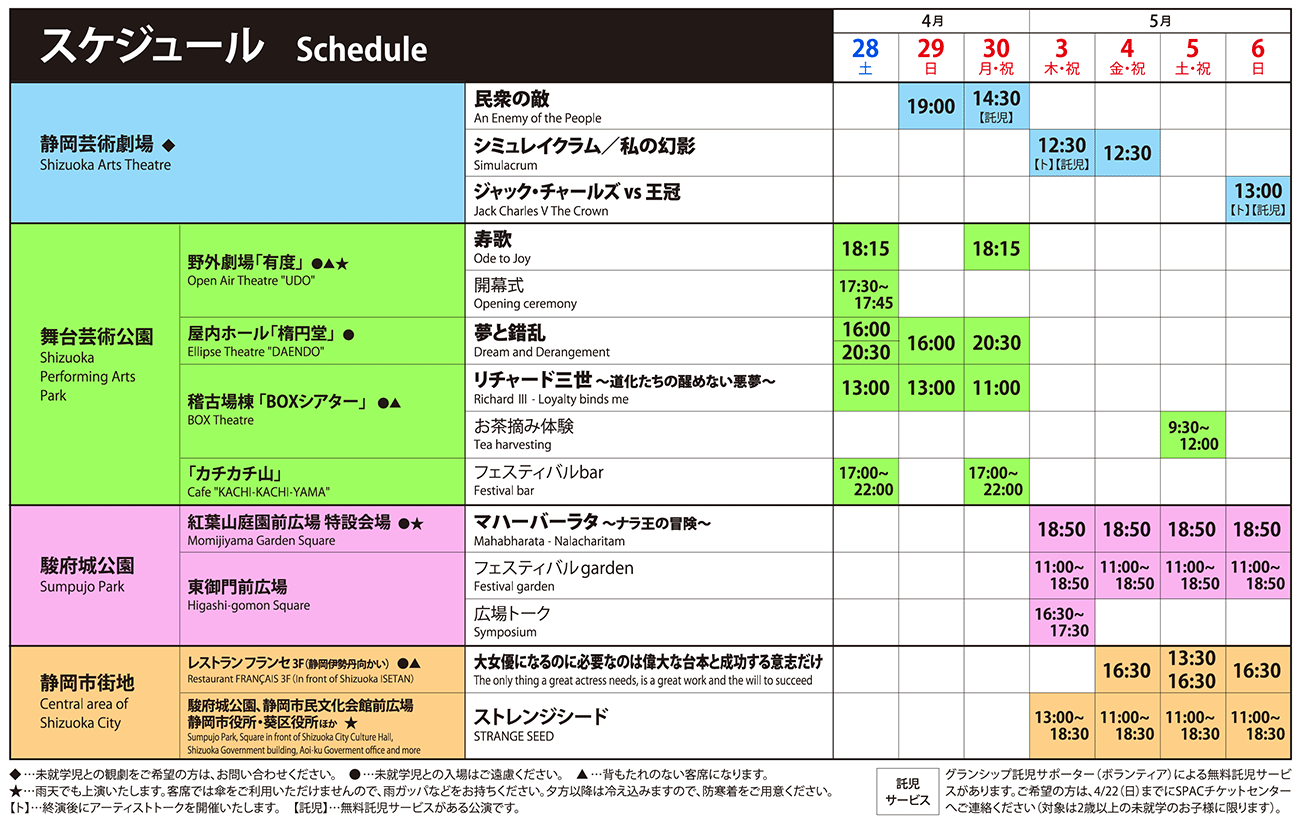メッセージ
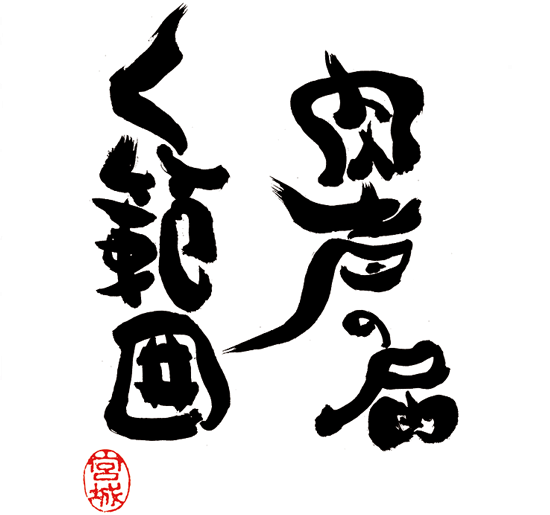
これらの人々は、決して「発信」しているのではない。
聞き手に「耳を傾けてもらおう」として命懸けなのだ。
たくさんの人に読まれているSNSをやっている人なら、間違ったことを書かないよういつも意識せざるを得ないのは言うまでもありません。「間違ったこと」と言っても「正しい/正しくない」という話ではなく「いまどんなことが叩かれるのか」を察知していないといけないという話です。なんとも受け身の判断基準ですね。
ツイッターもフェイスブックもやっていない、という人でも、いまや人前で行動する時にはつねに「間違わないよう」気にしなければなりません。見ている人聞いている人がSNSで拡散する可能性があるし、それで何かの拍子に、ハラスメント、とか、ブラック、とか名指されたら、ちょっと立ち上がれませんから。
日本だとこの「間違わない」は「空気を読む」と似ていますが、「コレクトネス」という言い方をしている国もあります。つまり誰もが、いろんな角度から「コレクトかどうか(間違っていないかどうか)」をチェックされているというわけですね。
誰もがつねに「コレクトかどうか」を監視されている社会、というのは昔からありますが(五人組とか隣組とか)、でもかつてのそれは、監視している人間の顔が見えていました。いまの監視は誰ともしれない膨大な人数からなされるので、昔よりソフトですが、そのぶん得体が知れず、不気味です。不気味である理由のひとつは、その監視から自分がはずれてしまうと「世界とのつながりが切れる」ように感じて、誰も「相互監視の網」から逃げようとしないことです。
で、この「コレクトネス(間違っていない)」なるものと相性が悪いのが「生理的に」というやつではないかと思います。生理的にどうこう、という言い方は最近あまり使えなくなりましたが、しかし人間は経験の蓄積から好き嫌いが決まってきますから、例えばある種のにおいを「生理的に受け付けない」と感じたり、ある種の人を「キモい」と感じたりします。その根拠はあくまで経験の蓄積に過ぎませんが、まるで本能がそう反応しているかのように感じるものです。
でも、その生理にもとづいて発言したり行動したりした人が叩かれる局面をいまや我々はしばしば目にします。それで「自分は叩かれたくない」と思えば、おのずと人前では当りさわりのないことだけ言うようになります。
でも、こうやって「間違わないように」とビビリながら当りさわりのないことを言い続けているうちに、ストレスはどんどん溜まってゆきます。「好きなものは好き、キモいものはキモい、と言ってなんで悪いんだ!」という気分が、体内でガスのように膨張してゆきます。
そんななか、「びくびくしていない」ように見える人がいます。それは「自分のキャラクターをじょうずに発信できた人」です。そのキャラクターが先に浸透していれば、そのひとの言動は「さもありなん」と受け止められ、キャラの枠内であれば自由気ままに発言できるようになります。つまり相互監視網のなかでの「勝者」ですね。
こういう勝者を見ると、「いまの時代、じょうずに自分を発信できるかどうかが勝敗の分かれ目だ」と感じられてきます。コミュ力は、イコール発信力である、と。
テクノロジーというのは、能動と受動では能動の側から進歩してゆきます。なので「じょうずに発信する人」は「ITをうまく使える人」とほぼ一致します。そういう先行走者をまのあたりにすると周囲の人々もITを使いこなして発信するようになり、発信のじょうずな人は増えてゆきます。で、いっこうに進歩しないのが「聞く」能力のほうですね。発信のほうはITの助力で自分の能力が拡張する実感があるので熱中できますが、「聞く」ほうは地味ですよね。「人の話に耳を傾けるためのIT」ってあまりありません。
どんな人もヴァーチャルな空間だけで生きていることはなくて、学校とか会社とか家庭では昔ながらに肉体同士が向かい合っているはずなんですが、でも「目の前の聞き手が自分の話に耳を傾けているのかどうか」を気にしなくていい発信オンリーのコミュニケーションに慣れてくると、聞き手の様子をケアすることがとっても面倒になってきます。結局、面と向かっていてもお互いに「発信ばっかり」の関係(相手の言うことは聞かないで自分の言いたいことだけ言う関係)が増えているのがこんにちの趨勢ですよね。
で、このまま進むとどうなるでしょうか?もしみんなが「勝者」になれるのなら、このままでもいいのかもしれません。でも、じょうずに自分を発信しているかに見える人たちの多くが本当は「置いていかれないよう必死」で、自分が勝者だという実感とはほど遠いところにいる、てなことになるのではないでしょうか。
そのとき、社会はこういう無言の叫びで満ちているでしょう。「あー、もう疲れた。ただ単に好き嫌いだけで言ったりやったりできる場があればいいのに!」
──排外主義が吹き荒れるのはこの瞬間でしょう。
「ふじのくに⇄せかい演劇祭」に集まるのは、「肉声を届ける」ことに全力で取り組んでいる人たちです。彼らは「発信」しているのではありません。聞き手に「耳を傾けてもらおう」と命懸けなのです。
宮城聰(SPAC芸術総監督)

宮城 聰 MIYAGI Satoshi
1959年東京生まれ。演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京大学で小田島雄志・渡辺守章・日高八郎各師から演劇論を学び、90年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出で国内外から高い評価を得る。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、「世界を見る窓」としての劇場づくりに力を注いでいる。14年7月アヴィニョン演劇祭から招聘された『マハーバーラタ』の成功を受け、17年『アンティゴネ』を同演劇祭のオープニング作品として法王庁中庭で上演、アジアの演劇がオープニングに選ばれたのは同演劇祭史上初めてのことであり、その作品世界は大きな反響を呼んだ。他の代表作に『王女メデイア』『ペール・ギュント』など。04年第3回朝日舞台芸術賞受賞。05年第2回アサヒビール芸術賞受賞。
ふじのくに⇄せかい演劇祭とは
SPAC-静岡県舞台芸術センターでは、1999 年に開催された世界の舞台芸術の祭典「第2 回シアター・オリンピックス」の成功を受けて、2000 年より「Shizuoka 春の芸術祭」を毎年行い、各国から優れた舞台芸術作品を招聘・紹介してきました。SPACが活動15年目を迎えた2011年からは、名称を「ふじのくに⇄せかい演劇祭」と改め、新たなスタートを切りました。
「ふじのくに⇄せかい演劇祭」という名称には、「ふじのくに(静岡県)と世界は演劇を通して、ダイレクトに繋がっている」というメッセージが込められています。静岡県の文化政策である「ふじのくに芸術回廊」と連携しながら、世界最先端の演劇はもちろん、ダンス、映像、音楽、優れた古典芸能などを招聘し、静岡で世界中のアーティストが出会い、交流する―そんなダイナミックな「ふじのくにと世界の交流(ふじのくに⇄せかい)」を理念としています。
SPAC-静岡県舞台芸術センター
静岡県舞台芸術センター(Shizuoka Performing Arts Center : SPAC)は、専用の劇場や稽古場を拠点として、俳優、舞台技術・制作スタッフが活動を行う日本で初めての公立文化事業集団であり、舞台芸術作品の創造・上演とともに、優れた舞台芸術の紹介や舞台芸術家の育成を事業目的とする。1997 年から初代芸術総監督鈴木忠志のもとで本格的な活動を開始。2007 年より宮城聰が芸術総監督に就任し、さらに発展させている。演劇の創造、上演、招聘活動以外にも、教育機関としての公共劇場のあり方を重視し、中高生鑑賞事業公演や人材育成事業、アウトリーチ活動などを続けている。2013年8月には、全国知事会第6回先進政策創造会議により、静岡県のSPAC への取り組みが「先進政策大賞」に選出された。