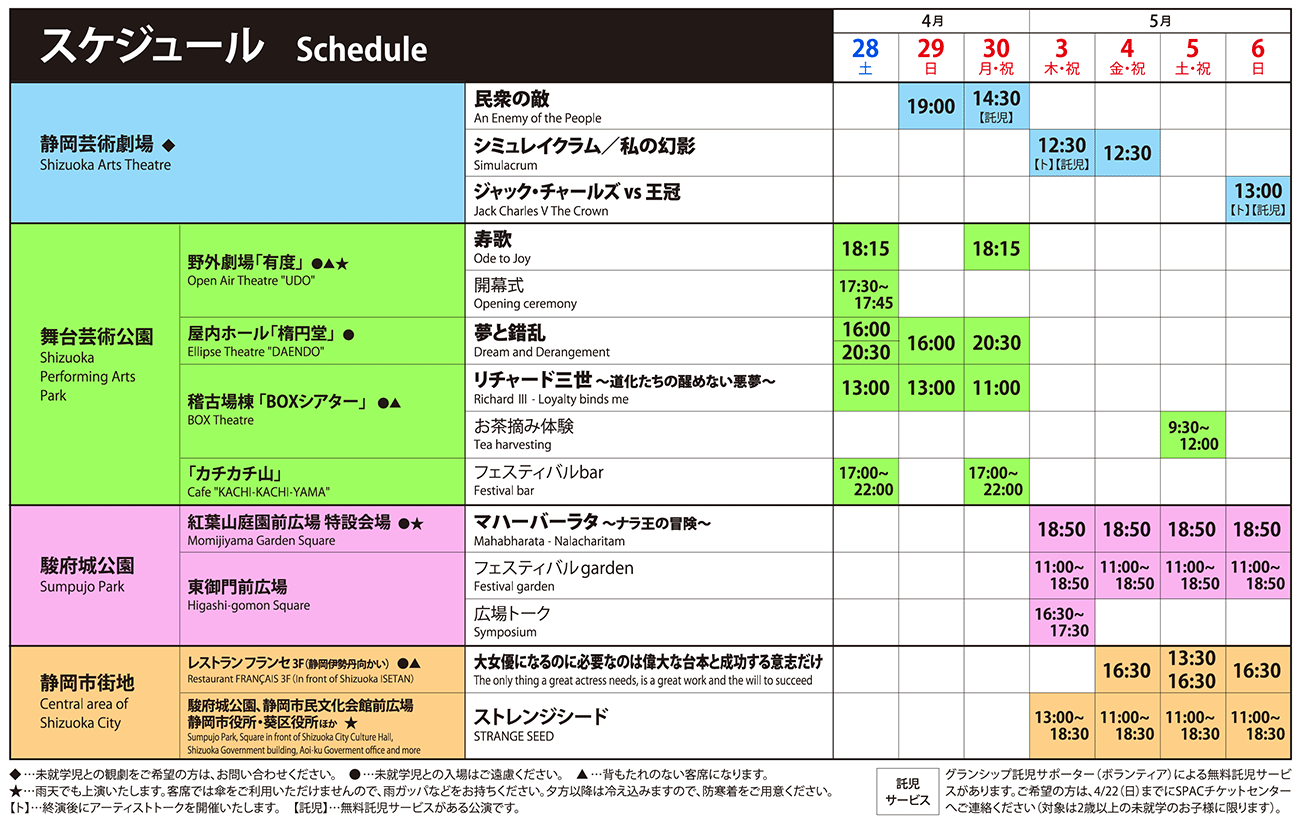寿 歌
© 松本久木
Program Information
| ジャンル/都市名 | 演劇/愛知・静岡 |
|---|---|
| 公演日時 | 4/28(土)18:15、4/30(月・祝)18:15 |
| 会場 | 舞台芸術公園 野外劇場「有度」 |
| 上演時間 | 90分 |
| 上演言語/字幕 | 日本語上演/英語字幕 |
| 座席 | 全席自由 |
| 演出 | 宮城聰 |
| 企画 | 愛知県芸術劇場、SPAC-静岡県舞台芸術センター |
作品について
今こそ宮城聰が寿ぐ、「現代の予言の書」
小劇場演劇の旗手として、今も名古屋を拠点に活動する劇作家・北村想が、1979年に発表した『寿歌』。80年代の小劇場演劇の潮流を決定づけたとも言われ、発表から約40年、上演が絶えることのない伝説の戯曲を、SPAC芸術総監督の宮城聰が初演出する。舞台は、核戦争によって荒廃した関西のとある地方都市。3人の旅芸人らがエエカゲンな会話を交わしながら、チンドンの歌や踊り、奇術を繰り広げていく。北村ならではの言語感覚で書かれた一見荒唐無稽な会話劇は、今と未来を黙示するかのよう。宮城はこれを「現代の預言の書」と捉え、新たに世に贈る。
野外劇場に現れる終末世界。“エエカゲン”喜劇が今を照らす。
過去には、出演者3人と彼らが家財道具を積んだリヤカー1台以外何もない舞台で上演されることが多い『寿歌』だが、今回は舞台美術家として活躍するカミイケタクヤにより、大掛かりな舞台セットが出現する。そして、愛知県芸術劇場での初演に続く全国ツアーで、静岡は唯一の野外上演。舞台に広がる終末世界に対し、それを取り囲む木々や鳥のさえずりが、今そこに流れる時間を観客に強く意識させることだろう。底抜けな明るさを湛えた“エエカゲン”喜劇が、宮城の演出により我々の生きる「今」を燦々と照らし始める。
あらすじ
核戦争後の荒野に、リヤカーを引いた旅芸人のゲサクとキョウコがやって来る。二人の頭上には、残りもんの核ミサイルが飛び交っている。そこにどこからともなく、自らをヤソ(ヤスオ)と名乗る謎の男が現れ、一座の旅に加わる。ホタルを追いかけていくキョウコ、曲芸をしくじって瀕死の重傷を負うゲサク。やがてあっけなく、ヤスオとの別れの時が来て・・・。キョウコが「寿歌」を口ずさむなか再びリヤカーが動きはじめる。
劇作家からのビデオメッセージ
演出家プロフィール

宮城 聰 MIYAGI Satoshi
1959年東京生まれ。演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京大学で小田島雄志・渡辺守章・日高八郎各師から演劇論を学び、90年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出で国内外から高い評価を得る。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、「世界を見る窓」としての劇場づくりに力を注いでいる。14年7月アヴィニョン演劇祭から招聘された『マハーバーラタ』の成功を受け、17年『アンティゴネ』を同演劇祭のオープニング作品として法王庁中庭で上演、アジアの演劇がオープニングに選ばれたのは同演劇祭史上初めてのことであり、その作品世界は大きな反響を呼んだ。他の代表作に『王女メデイア』『ペール・ギュント』など。04年第3回朝日舞台芸術賞受賞。05年第2回アサヒビール芸術賞受賞。平成29年度(第68回)芸術選奨文部科学大臣賞(演劇部門)受賞。
劇作家プロフィール

北村 想 KITAMURA So
1952年生まれ。独居独身。84年『十一人の少年』で第28回岸田國士戯曲賞、90年『雪をわたって…第二稿・月のあかるさ』で第24回紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞。96年より兵庫県伊丹市のアイホールにて、戯曲講座「伊丹想流私塾」(2017年より「伊丹想流劇塾」と改名、現在は名誉塾長)を開塾、後進の指導、育成にあたる。14年『グッドバイ』で第17回鶴屋南北戯曲賞受賞。
関連企画
◎開幕式:4/28(土)17:30~17:45 会場/舞台芸術公園 野外劇場「有度」前広場
出演者/スタッフ
演出:宮城聰
作:北村想
美術:カミイケタクヤ
照明デザイン:木藤歩
出演:SPAC/奥野晃士、春日井一平、たきいみき
照明操作:林大貴(A)
音響デザイン:佐々木道浩(A)
音響操作:服部竜平(A)
衣裳デザイン:駒井友美子(S)
衣裳助手:川合玲子(S)
演出補:中野真希(S)
宣伝美術・写真:松本久木
舞台監督:世古口善徳(A)
舞台監督助手:加藤元基
演出部:峯健(A)、二瓶はるか(A)、神谷俊貴(S)
美術助手:竹腰かなこ、佐藤洋輔(S)、渡辺宏規(S)
英語字幕翻訳:三田地里穂
字幕操作:ながいさやこ(S)
制作:伊藤友美(A)、上林元子(A)、小森あや(A)、内田稔子(S)、雪岡純(S)、仲村悠希(S)
プロデューサー:山本麦子(A)
技術監督:村松厚志(S)
照明統括:樋口正幸(S)
音響統括:加藤久直(S)
照明:藤田隆広、久松夕香、佐藤花梨(S)
音響:杉藤芳明(S)
シアタークルー(ボランティア):越智良江、立林学、松本孝則
企画:愛知県芸術劇場、SPAC-静岡県舞台芸術センター
制作:愛知県芸術劇場
支援:平成三〇年度 文化庁 国際文化芸術発信拠点形成事業 
(A)・・・愛知県芸術劇場
(S)・・・SPAC-静岡県舞台芸術センター
上演許可番号:So Kitamura 2017 No.0021 岡野宏文
寄稿
瓦礫の荒野と蛍の光 ――北村想『寿歌』における聖性
安住 恭子
北村想の『寿歌』は、戦後の日本の戯曲の中で、最も上演回数の多い作品といってもいいのではないだろうか。北村が書いてから40年ものときがたつのに、今なおどこかしらで上演されているのだという。それぞれのカンパニーが新作戯曲を上演することの多い日本の現代演劇の中で、それはかなり特異なことだ。なぜこの作品は、それほど演劇人を引きつけるのだろう。
おそらくその秘密は、この戯曲がはらむ透明な明るさと切なさにあるのではないだろうか。核戦争が終わった瓦礫の荒野を、旅芸人のゲサクとキョウコがあてもなく歩いている。するとその前に、ヤスオという男が現れ、3人はひととき共に旅をする。ただそれだけの話である。ゲサクとキョウコの会話も芸も、まるで冗談のようにいいかげんで、戦争で多くの人が亡くなったことや、仲間と行きはぐれたことなど、まったく意に介していない。それらへの屈託は一言も語らずに、リチウム爆弾の炸裂を花火のように眺めているのだ。つまり彼らは終末の世界に、純な生命体としてただポツンといる。この、一面の荒野にポツンと在る小さな生命という設定が、透明な明るさと切なさを、まずは引き起こすのだと思う。
闇に小さく光る蛍のように彼らは在るが、その光は旅芸人という生き方から発している。たとえどんなに拙くいいかげんではあっても、芸は彼らの存在証明であり、それを糧に生きている。このことは、『寿歌』を書いた当時、27歳の北村想が、演劇と共に生きていくと決意したことの象徴ではないか。戦争や災害のあるなしにかかわらず、生きることは荒野を渡っていくことだ。瓦礫の荒野は常に目の前にある。生きることは切なく厳しい。それを渡る1つの力として、北村は演劇を選んだ。魅力的なおもちゃでありながら、その創造が豊かな想像力をひろげ、心の糧となる。「戯作狂言」から名付けられたゲサクとキョウコは、共にその演劇の精なのだ。とりわけ無垢なキョウコの有り様は、聖性さえ感じさせる。北村は演劇をそのように発見し、軽やかに戯れることを選んだ。その発見の喜びが、『寿歌』というタイトルの理由の1つだろう。
では、ヤスオとは何か。それは劇中でゲサクが語るように、「ヤソ」つまり神だろう。実はこの戯曲は、ペテロとアンデレの兄弟がガラリア湖畔でキリストに出会った、「新約聖書」のパロディのようにつくられている。けれども『寿歌』から聖書を思い浮かべることは、あまりないようだ。それはこのヤソ像が、いかにも無力で頼りないからだ。「物品取り寄せの術」なる力はあるものの、厳しく偉大なキリスト像からは遠くかけ離れている。彼は教えを説くわけでもなく、罪を問い、罰や救済を与えるわけでもない。むしろ配ったロザリオにカミナリが落ちるという、災いをまねく存在だ。けれども北村想は、そのようなヤソをこそ神とし、信じたいと思ったのではないか。上から教え導く神ではなく、横に並び、ひととき一緒に歩いてくれる神。現世のことにうとく、夢見る少年のような神。北村は当時やはりキリスト教に近づいているが、自分なりの神をそのように発見した。その発見もまた喜びであり、『寿歌』というタイトルのもう1つの理由にちがいない。
ではなぜ、そのような神を思い描いたのだろうか。それは観念としてでなく、現実に、瓦礫の荒野を目の前にしたからではないか。単なる不条理の体験ではない。「生きるとは何か」と深く深く問わずにはいられないほどの、生きがたさを感じたのだと思う。それは青年期特有の憂鬱症だったかもしれない。しかし、心の危機ではあった。そう思うのは、ゲサクが語る衝撃的なウサギのエピソードによる。雪山で倒れていた主人を救うために、ウサギがたき火に飛び込み、自らウサギの丸焼きをつくったという話だ。これは仏教の菩薩道を説く説話だが、ゲサクはそれを、菩薩道でも貴い犠牲的精神でもなく、「うさぎが命を賭けて報いた仕業もせいぜいがえさになることだったんや」と解釈するのだ。この「生きる悲しさ」が分かるか、と。たった1食分の値でしかない命。その命を生きるしかない私たち。
この身を切るような悲しみに対応できるのは、尊い説教の言葉でもなければ、現世利益でもないだろう。ただひとときそばに寄り添い、ずっと遠くを夢見る眼差しによって、わずかの安らぎと慰めを与えることのできる神。北村はそんな神を自分の中に創造した。そして『寿歌』は、それら演劇と神に対する思いを率直につづった1編なのだ。深い絶望と同時に、発見の喜びがある。虚無感と同時に明るさがある。切なさと同時に笑いがある。そして演劇と神と共に生きるという決意がある。それらを全部飲み込んで、1編の象徴的な詩が吐き出された。
今回、宮城聰演出の『寿歌』は、静岡の舞台芸術公園で、野外で上演される。この作品が野外で演じられるのは、私の知る限りでははじめてのことだ。阪神や東日本の大震災のあとに、現実の瓦礫のなかで上演しようという話は何度かあったと聞くが、実現しなかった。ゲサクとキョウコとヤスオが、はじめて外の闇と風と月明かりに立つのだ。カミイケタクヤの、メビウスの輪のような、あるいは永遠を表す∞のような舞台美術が、3人の道程を象徴する。「ちょっとそこまで」と「ずっとむこうまで」は同じであり、「あっちはどっちや」という世界だ。その世界でゲサクとキョウコは、いつかまたヤスオにめぐりあうかもしれないし、どこかですれちがうかもしれない。悲しみを胸に、永遠にその道を歩いて行くヒトの姿を、私たちは見るのかもしれない。
<筆者プロフィール>
安住 恭子 AZUMI Kyoko
演劇評論家。元読売新聞記者。記者時代から雑誌「新劇」「演劇界」などに演劇評論を執筆。現在は、中日新聞などに演劇評論を連載。また、シアターコクーンで上演した『RASHOMON』(野村萬斎演出・主演)の脚本を担当したほか、プロデューサーとして、『百人芝居◎真夜中の弥次さん喜多さん』など、プロデュースも多数行っている。著書に、『青空と迷宮――戯曲の中の北村想』(小学館スクエア)、『「草枕」の那美と辛亥革命』(白水社)など。同書で「和辻哲郎文化賞」受賞。名古屋市芸術奨励賞受賞。