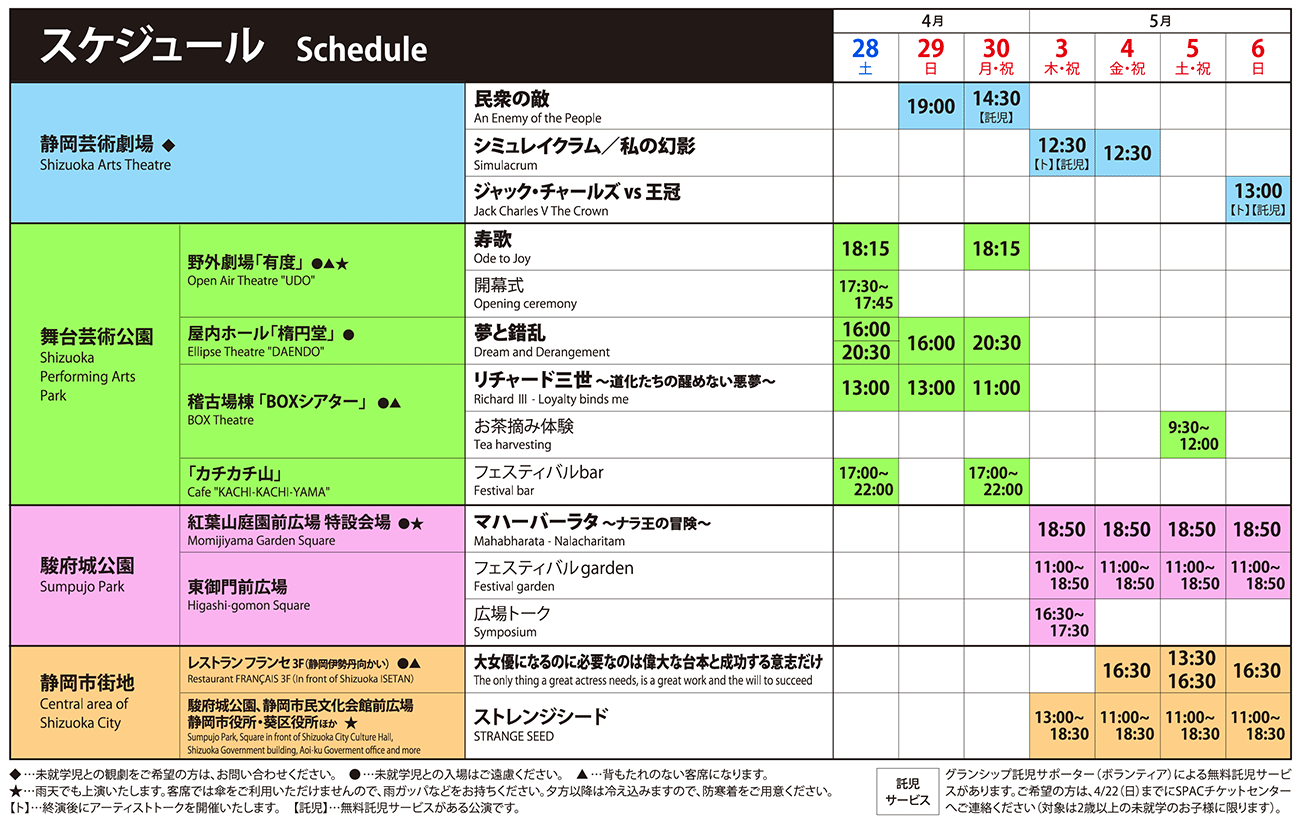大女優になるのに必要なのは偉大な台本と成功する意志だけ
© Paula PRIETO
Program Information
| ジャンル/都市名 | 演劇/メキシコ・シティ |
|---|---|
| 公演日時 | 5/4(金・祝)16:30、5/5(土・祝)13:30、16:30、5/6(日)16:30 |
| 会場 | レストラン フランセ 3F(静岡伊勢丹向かい) |
| 上演時間 | 50分 |
| 上演言語/字幕 | スペイン語上演/日本語字幕 |
| 座席 | 全席自由 |
| 演出・作 | ダミアン・セルバンテス |
| 製作 | Vaca35(バカ35) |
作品について
「ごっこ遊び」は空腹を満たす?
演出家ダミアン・セルバンテス率いるVaca35(バカ35)は、2007年に旗揚げされたメキシコの若手劇団。本作は、12年メキシコ国立劇場での初演以降、スペインやキューバなど世界各地で200回以上も上演を重ね、この度、初来日する。狭く薄汚れた部屋で、巨体と痩せぎすの二人の女が興ずるのは「奥様と女中ごっこ」。ジャン・ジュネの『女中たち』よろしく、やり取りはエスカレートし、唐突に演技を中断した後も二人は余韻に浸る。しかし現実に横たわる貧困と孤独が寄せては返し、ふとしたことで二人は罵り合い、そして空虚に襲われ・・・。戯れはしかし孤独と貧困を一時忘れるためではない。物語ることの根源的な力が日常を支える、そんなことをまざまざと見せてくれる珠玉のドラマ。
女優二人による肉弾格闘演技!極小空間にひしめく物語。
本作が上演されるのは、静岡の繁華な商店街に建つ昭和30年代に建てられたビルの一室。かつて結婚式場として使われていた空間には人の気配が残る。女優二人はセリフをまくし立てながら、観客から手が届きそうな距離でモップがけ、洗濯、料理、たらいでの沐浴など、日常の作業を気ぜわしく行う。そして互いがサンドバッグであるかのように愛情や不満のすべてをぶつけ、殴り合い、許し、労わり合うのだ。匂い、湿度など、劇場とは異なる緊密な空間でのみ得られる演劇体験がここにある。
あらすじ
薄汚れた部屋、二人の女が奥様役と女中役になりきり、セリフをまくしたてている。突然かかる「カット」の声。二人は互いの演技を褒めちぎり、興奮に酔いしれる。演技へのダメ出しにも飽き、パンをかじるも満たされない。ふと出た不平不満から醜い罵り合いに。やがて喧嘩の熱も覚め、互いを労るように口をついたのは、お姫さまのおとぎ話だった。
演出家プロフィール

ダミアン・セルバンテス Damian CERVANTES
1981年メキシコ生まれ。俳優・演出家。2007年に劇団Vaca35を立ち上げる。本作は12年メキシコで初演、スペインやサラエボなど各地で200回以上上演されている。
出演者/スタッフ
集団創作:劇団Vaca 35(バカ35)
演出・脚本:ダミアン・セルバンテス
出演:ディアナ・マガジョン、マリ・カルメン・ルイス
エグゼクティブ・プロデューサー:ホセ・フローレス・チャベス
製作:Vaca35(バカ35) ![]()
助成:メキシコ国立文化芸術基金 
SPACスタッフ
舞台監督:川上大二郎
舞台:内野彰子、折本弓佳
通訳:森直香
字幕翻訳・操作:古屋雄一郎
制作:雪岡純、林由佳
シアタークルー(ボランティア):松浦康政、セバスティエン・ボネ
技術監督:村松厚志
照明統括:樋口正幸
音響統括:加藤久直
支援:平成三〇年度 文化庁 国際文化芸術発信拠点形成事業

注意事項
・一部刺激の強い表現があります(12歳以上推奨)。
・受付・集合場所:静岡市役所(葵区役所)、青葉通り側の駐輪場上の噴水前広場
開演の20分前より、チケットに記載された整理番号順に会場へご案内いたします。
寄稿
見られていなくても踊ることをやめない
神里 雄大
去年の1月に10日間ほど、ぼくは南米チリの首都サンティアゴに滞在していた。そこでは毎年1月に、「サンティアゴ・ア・ミル」という国際演劇フェスティバルが開かれていて、そのとき観た作品のひとつが、『大女優になるのに必要なのは偉大な台本と成功する意志だけ』だった。そういう縁でこれを書いている。だが、ぼくの拙いスペイン語力では、早口でまくし立てられるセリフを追えるわけもなく、今回台本を読ませてもらって初めて、この作品がジャン・ジュネの『女中たち』をモチーフにしたものだということがわかったくらいなので、知ったかぶりをして作品を解説することはできない……。
『女中たち』は、主人のいない間にメイドたちが、主人(奥様)とメイドの役をそれぞれ演じて遊んでいたら、だんだんと現実と虚構が混ざってきてしまって、奥様を殺そうという計画を練る──というような話。でも、ぼくには『女中たち』についての考察を書ける気もしないので、これも止すことにする……。
ぼくに書くことができそうなのは、せいぜい自分がこの作品を見たときの話くらい。なぜかというと、何者か別の誰かになる気がぼくにはないから。
36度を超える暑い夏のサンティアゴの日中に、地下鉄に乗ってぼくは会場に向かった。そこはたしか大学の施設で、中に入るとすぐに庭があって、それを3階建ての建物が囲んでいた。すでに何人かの観客らしき人間たちがいたので、ぼくもそれに習って中庭にあったベンチに座り、案内されるのを待った。みんな本を読んだり、友人たちと会話したりしていた。ベンチでぼくはひとり、赤い色のジュースを飲んで待っていた。開演時間をだいぶ過ぎてから、ようやく会場の外に列が作られ並び、すると演出家のダミアン・セルバンテスらしき人物が観客にメスカル(メキシコの酒)を振る舞い出したので、ぼくももらって飲み干した。会場のなかに入ると、予想していたよりもずっと狭いスペースだった。平日の昼の回だったということも理由なのか、観客は12人くらいしかいなくて、ほろ酔いの頭が不安になった。開演の直前に、ぼくの隣にダミアン・セルバンテスらしき人物が座ったので、さらに緊張が加わった。
ぼくたちは日差しの強い夏の日、わざわざブラックボックスのなかで、暑苦しい演技を観た。まるでわからないセリフ。12人しかいない観客のひとりが謎の日本人で、客席に座っているけれどもまるでセリフを理解していない。というのを、熱演する俳優たちが知ったら彼女たちはどう思うのだろうか。じっさい彼女たちは、観客がどんなふうになっているのかなど、気にせずに演技しているように見えた。俳優という人間たちは、体ひとつで人前に出てきて、動かない観客のまえで暴れ回るのである……。
わけもわからず、彼女たちが動いたりしゃべったり静かにしたりするのを見つめながら、ぼくは自分が「正しい観客」であろうとする感覚を捨てるように努めることにした。つまり、(そもそもわからない)セリフを追うことや、それに伴う身体状況を観察するということをしないように、何事にも意味を見出さないように、自分の価値観から俳優たちや演出のことを判断しないように。わからないことをそのまま受け入れるということ。そこから、メキシコからやってきた彼らの正体に近づけるかもしれない、などと考えた。それくらいしかできそうなことがなかった。
ところで、『女中たち』についての考察を書くのは止めると書いたが、ひとつだけ思うことを書くとすれば、ぼくにとって『女中たち』は、童謡「おもちゃのチャチャチャ」を想起させる。日頃の従順さから抜け出して、おもちゃたちは夜な夜なパーティをするわけだが、いくら深夜とはいえどんちゃん騒ぎを始めたら、子どもは起きてしまわないだろうか。
しかし、子どもは起きないのである。なぜならその騒ぎは、子どもにとってひどく小さく、取るに足らない音量で行われているために、気づくことができないからだ。おもちゃの騒ぎは誰にも聞こえることはない。誰にも気づかれないということは、存在していないことと一緒だ。どんちゃん騒ぎの事実を、第三者である、自分たちの所有者の子どもに認識されないおもちゃたちは、いつかそのことを知って徐々に虚しくなってしまう。その表情には悲しみが浮かんでいるものの、けっきょく見ているものがいないので、本当には悲しんでいるのかどうかもわからない。
<筆者プロフィール>
神里 雄大 KAMISATO Yudai
作家、演出家。1982年生まれ。文化庁の新進芸術家海外研修員として、2016年10月から2017年8月までアルゼンチンのブエノスアイレスに滞在した。