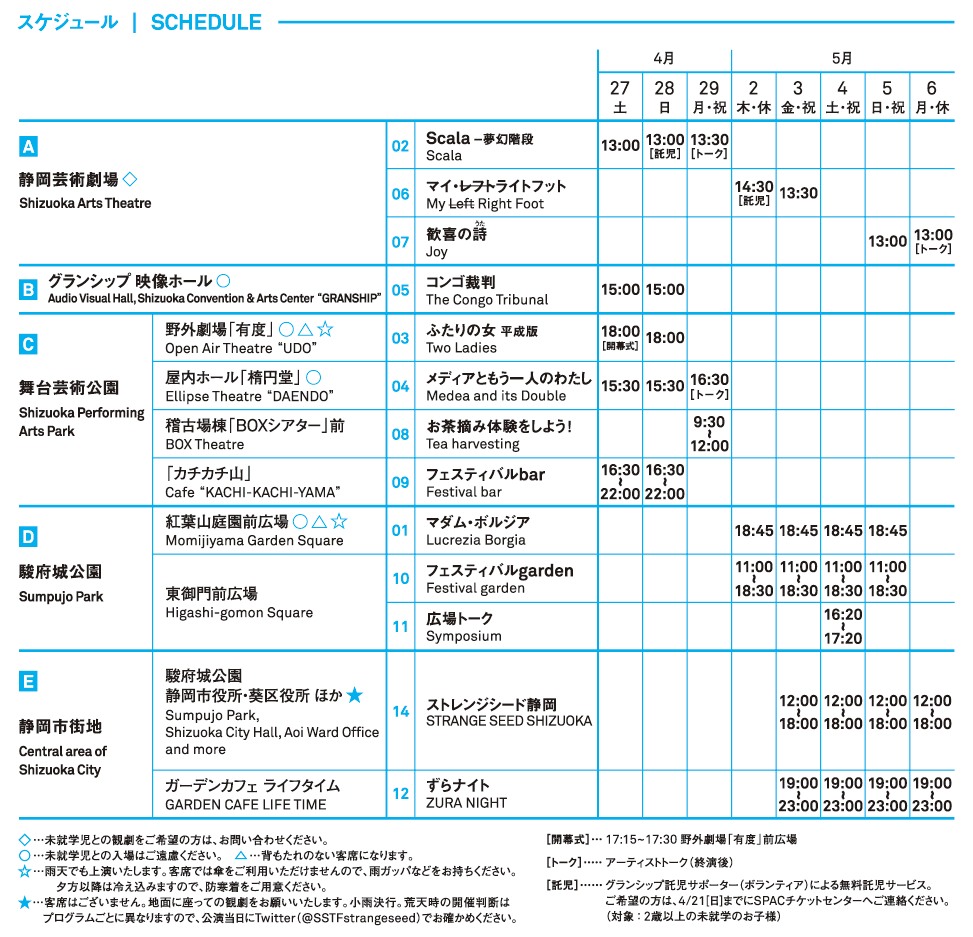ふたりの女
平成版 ふたりの面妖があなたに絡む© 日置真光
Program Information
| ジャンル/都市名 | 演劇/静岡 |
|---|---|
| 公演日時 | 4/27(土)18:00、4/28(日)18:00 |
| 会場 | 舞台芸術公園 野外劇場「有度」 |
| 上演時間 | 80分 100分 |
| 上演言語/字幕 | 日本語上演/英語字幕 |
| 座席 | 全席自由 |
| 演出 | 宮城聰 |
| 製作 | SPAC-静岡県舞台芸術センター |
作品について
アングラ・小劇場演劇へのオマージュが炸裂する、これが宮城演出もう一つの顔!
1960年代アングラ・小劇場演劇シーンを象徴する劇作家・演出家、唐十郎。その戯曲には、猥雑さをない交ぜにした時代のエネルギーが凝縮され、詩的・音楽的なセリフ群は輝きを放ち続ける。『ふたりの女』は、『源氏物語』の光源氏と妻・葵上、生霊となった六条御息所の三角関係に、狂気と正気の境界を描くチェーホフの『六号室』を巧みに織り込んだ傑作。世界の演劇シーンで確固たる存在感を示す宮城聰が、極小空間での伝説的初演を深くリスペクトしつつ、その演出術を縦横無尽に駆使し、唐戯曲を日本平の古代の森の野外空間へと解き放つ。2009年の初演から大入り満員を続けるSPAC野外劇のテッパン、待望の再々演!
あらすじ
伊豆の砂浜に立つ精神病院。イケメン医師・光一は、六条という名の美人患者に声をかけられ、不意にアパートの鍵を渡されてしまう。富士スピードウェイで妊娠中の妻・アオイとレース観戦をしていた光一、アオイが席を外した隙に、退院した六条が現れ…。
演出家プロフィール

宮城 聰 MIYAGI Satoshi
1959年東京生まれ。演出家。SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督。東京大学で小田島雄志・渡邊守章・日高八郎各師から演劇論を学び、90年ク・ナウカ旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出で国内外から高い評価を得る。2007年4月SPAC芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、またアウトリーチにも力を注ぎ「世界を見る窓」としての劇場運営をおこなっている。17年『アンティゴネ』をフランス・アヴィニョン演劇祭のオープニング作品として法王庁中庭で上演、アジアの演劇がオープニングに選ばれたのは同演劇祭史上初めてのことであり、その作品世界は大きな反響を呼んだ。他の代表作に『王女メデイア』『マハーバーラタ』『ペール・ギュント』など。2004年第3回朝日舞台芸術賞受賞。2005年第2回アサヒビール芸術賞受賞。2018年平成29年度第68回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。
劇作家プロフィール

唐十郎 KARA Juro
1940年東京生まれ。明治大学文学部演劇学科卒業。63年「劇団状況劇場」を旗揚げ。実験精神と独自性に富む街頭での野外劇を試みるなど、小劇場運動の先陣を切った。67年新宿花園神社に初めて紅テントを建て『腰巻お仙』を上演。以後テント公演を中心に活動、海外公演も行う。70年『少女仮面』で岸田國士戯曲賞、82年『佐川君からの手紙』で芥川賞など受賞歴多数。88年「劇団唐組」を結成。劇団を率い、現在までほぼ年2回のペースで新作上演を続けている。また、ドラマ、CM出演等、俳優としての活躍は演劇、映画にとどまらない。
出演者/スタッフ
演出:宮城聰
作:唐十郎
出演:たきいみき、石井萠水、奥野晃士、春日井一平、木内琴子、武石守正、舘野百代、永井健二、三島景太、吉見亮、若宮羊市
<スタッフ>
装置デザイン:村松厚志
照明デザイン:樋口正幸
音響デザイン:金光浩昭(㈱三光)
衣装デザイン:畑ジェニファー友紀
ヘアメイクデザイン:梶田キョウコ
舞台監督:渡部景介
演出助手:守山真利恵
演出部:神谷俊貴
照明操作:久松夕香
音響操作:和田匡史
ワードローブ:川合玲子
美術担当:渡部宏規
ヘアメイク:高橋慶光
英語字幕翻訳:エグリントン・みか、アンドリュー・エグリントン
英語字幕操作:Ash
制作:内田稔子、久我晴子
技術監督:村松厚志
照明統括:樋口正幸
音響統括:右田聡一郎
製作:SPAC-静岡舞台芸術センター
助成:文化庁 国際文化芸術発信拠点形成事業
注意事項
◎未就学児との入場はご遠慮ください。
◎背もたれのない客席になります。
◎雨天でも上演いたします。客席では傘をご利用いただけませんので、雨ガッパなどをお持ちください。夕方以降は冷え込みますので、防寒着をご用意ください。
寄稿
唐十郎『ふたりの女』あるいは〈数〉と〈名〉の戯れをめぐって
八角聡仁
一瞥して目に触れるとおり、唐十郎『ふたりの女』には数字が氾濫している。作者の名前には10、タイトルには2、登場人物には1(光一)や6(六条)、舞台の一つとなるのは病院の六号室、中心的イメージの砂=sandは「三度」と掛けられ、初演したのは劇団「第七病棟」だった。あるいはまた冒頭の場面にはこんな台詞がある。「そこで我々が悩まなければならないのは、十一の反革命性に気づいた時、指は十本しかないのだからして、その足らないもう一本をどこから見つけてくるかということだ!」。
これをどう捉えるべきか。もちろん、後述するように1と2の戯れや葛藤ならば、唐作品に繰り返し現れる「鏡」や「影」(あるいは「分身」)のテーマから読み解くこともできる。11本目の指の探索を『下谷万年町物語』の「六本指」をはじめとする、身体の過剰や欠損をめぐる主題系に連ねて考えることも可能だ。しかし、無方向に散乱する数字はそうした文脈から砂粒のように零れ落ち、トータルに意味づけることを拒んでいる。数はそれ自身として意味を持たない「形式」であり、非‐意味である、ということをまずは確認しておこう。唐十郎の作品が一貫して実践しつづけてきたのは、まさしく「意味」との闘いにほかならないからだ。
意味を透明に媒介する記号としてではなく、質量や触感を伴った「もの」として言葉を受けとめること。唐十郎の魅惑的な劇世界に入っていくために求められる唯一の条件はそれだろう。意味がないのではない(「無意味」もまた一つの意味である)。そこでは言葉によって指示される対象と、言葉それ自身が同じように「もの」として転がっている。
砂浜という客観物があるから、「砂浜」という名辞で呼ばれるわけではない。砂浜を砂浜として知覚するのは既に記号の作用にほかならず、砂浜という言葉と指向対象としての砂浜は同時に生起する。だから「サンド」が「サウンド」へと横滑りすれば砂が音を奏で始め、「カンカン帽子」は「影法師」を呼び寄せるだろう。そうした言葉の運動を一義的に固着させ、空間的な秩序へと回収するのが「意味」であるなら(登場人物たちも自らの身体と空間の不和をしばしば口にする)、それに対する抵抗を端的に示すのが数であり、そしてやはり劇中に氾濫する固有名なのだ。
唐の戯曲には『ふたりの女』と同様に、既存の映画や小説のタイトルをそのまま借用したものが少なくない(『二都物語』『秘密の花園』『黒いチューリップ』等々)。しかし、いずれも元の作品との内容的なつながりはなく、固有名が「もの」として召喚され、まったく異なる物語が同一のタイトルを持つことになる。一方で確かに『ふたりの女』の物語や人物配置は、『源氏物語』の「葵」の巻、あるいは謡曲『葵上』に基づいているとはいえ、誰もが知る古典から隠れた魅力を引き出そうとか、伝統芸能との血縁関係を主張しようなどといった考えが作者にあったとは到底思えない。たまたま手にすることになったありきたりの題材を、チェーホフの小説やデ・シーカの映画やパット・ブーンの歌詞と織り合わせてみたということだろう。唐の戯曲はほぼ例外なく先行する何らかのテクストを「読む」ことによって成立しているが、唐自身が「誤読」とも呼ぶように、それは文化的な起源に遡行する行為ではない。起源としての1はどこにもなく、差異から差異へと拡がる起源ならざる複数の起源の影が戯れているばかりだ。
初期の演劇的マニフェストとして知られる「特権的肉体論」(1968)は、「病者」(「悲しい叔父さん」とも言われる)としての中原中也論から書き起こされ、「なか」(中間)という世界の考察で結ばれる。時に誤解されるように、決して異形の身体が持つ「特権」を称揚しているわけでも、演劇における戯曲や言葉の機能を否定しているわけでもないことはともかく(そうした「誤読」も唐は想定済みだろう)、始めと終わり(それが「意味」を作り出すわけだが)に「中」が置かれるという迷宮的な構成にも着目したい。
唐の作品に頻出する「相似」の主題もそこに関わっている。何かと何かが互いに似ていることの不気味さ。起源を異にするものが重なり合い、ほとんど同じだが僅かに違っているという中間領域が滲み出す。始まりも終わりも欠いたその「なか」の時間において、砂に書かれては消える文字のように、そのつど一度限りの出来事として現れるものこそ「特権的」な何ものかであるにちがいない。
<筆者プロフィール>
八角聡仁 YASUMI Akihito
批評家、近畿大学文芸学部教授。1963年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。文学、演劇、ダンス、写真、映画などに関する論考多数。共著に『土方巽-言葉と身体をめぐって』(角川学芸出版)、『寺山修司の時代』(河出書房新社)他。