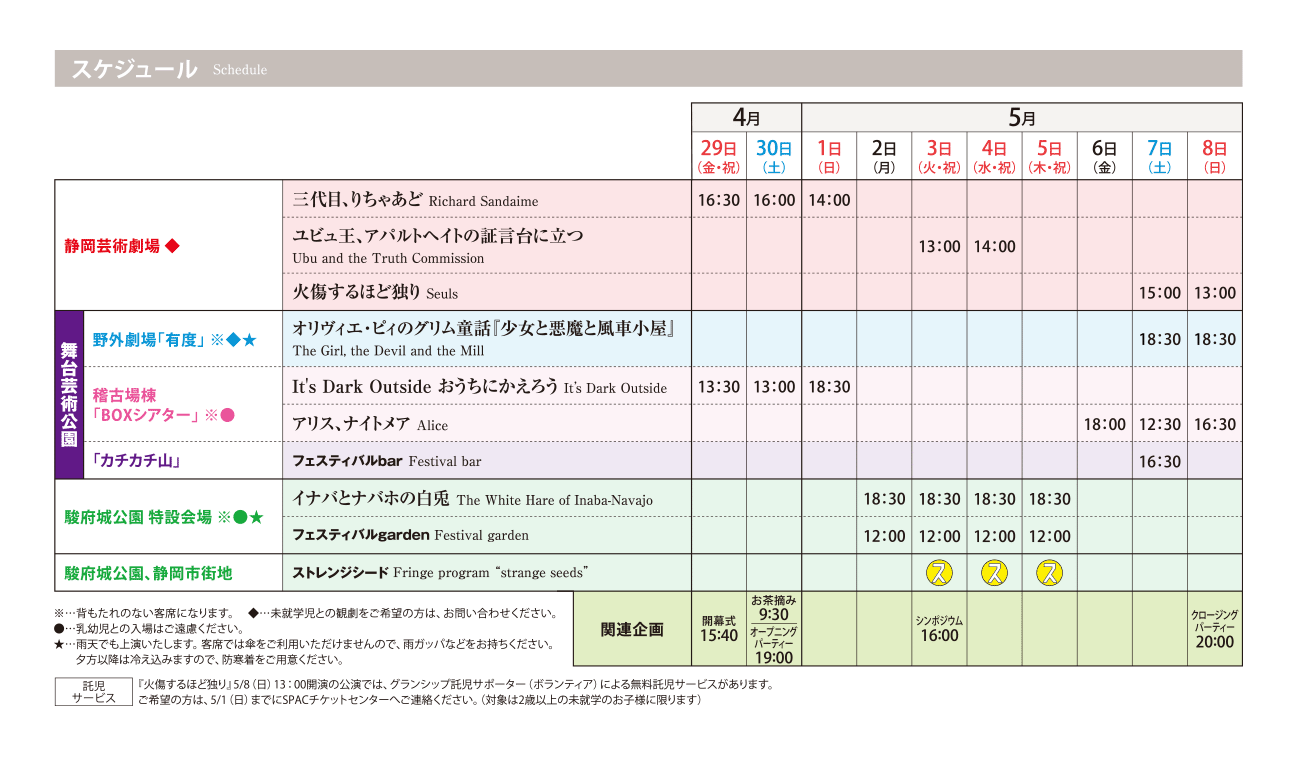SPAC文芸部 横山義志
ティム・ワッツはオーストラリア大陸の西南にあるパースという町を拠点として人形劇を作っている。パースは「世界で最も孤独な都市」と呼ばれていたりする。オーストラリアの大都市のほとんどは東部にある。パース都市圏の人口は約150万。西オーストラリア州の人口は250万人だが、90%は砂漠あるいは半砂漠地帯で、ほとんどの住民がパースの周辺に住んでいる。南に行けば南極、西に行けば南アフリカ、東に行けばチリの南端パタゴニアに行き着く。2012年の演劇祭で上演してくれた『アルヴィン・スプートニクの深海探検』の冒頭では、地球温暖化で海面が上昇した世界を舟で一周する場面があるが、パースからの「世界一周」は、私たちがイメージするのとだいぶ異なっていた。
なぜこんなところに大都市ができたのか。それは鉱山があったからだ。今でも鉱業が主要な産業の一つになっている。町から一歩出れば、広大な砂漠地帯が広がる。パースから車を飛ばして他の西部の町まで行くのはけっこう命がけらしい。数百キロ走っても対抗車に出会わなかったりする。途中でカンガルーが飛び出て、ぶつかって車が故障したりしたら、歩いて行ける範囲には誰も住んでいないかも知れない。だからオーストラリア人は車を修理するのがうまいという。シドニーまでは電車で48時間と聞いた。シドニーよりもジャカルタやシンガポールの方が距離的には近かったりする。
オーストラリア人は奥地の集落に住む「ブッシュマン」に憧れ、そのさらに奥にある「アウトバック」と呼ばれる荒野にこそ「本物のオーストラリアがある」という。『It’s Dark Outside おうちにかえろう』では、老人がそんな荒野へと旅立っていく。西部劇をイメージした、とワッツは語っていたが、アメリカの西部とオーストラリアの西部とが入り混じっているようにも見える。若いヒーローを描いた『アルヴィン・スプートニク』から一転して、老人を主人公にした作品と聞いて、ちょっと驚いた。二作品に共通するのは、強烈な孤独感だ。自分の住む町に、人類はもう自分しかいないかも知れない、というくらいの孤独。スプートニクは恋人を失って孤独になり、海底探検へと旅立つのだが、『It’s Dark Outside』では、はじめから孤独な老人が、さらに孤独になるために、荒野へと足を踏み出していく。
ここでは、認知症患者によく見られる「夕暮れ症候群」が描かれている。夕暮れ時になると、アパートやホームを出て、町をさまよう。日が暮れる頃に、あわてて仕事を終わらせて家に帰ったり、帰ってくる人のために家に戻って食事を作ったり、という記憶の名残だともいう。その安住の地が「わたしの家」ではない、という感覚もそこにはある。『It’s Dark Outside』では、老人は一言も話さない。そもそも話す相手がいないのだから。だが、同伴者を見つけ、言葉は交わさなくても、気持ちを通わせるようになる。そして荒野に自分の居場所を求めていく。認知症患者の世界をこれほど詩的に描いた作品があっただろうか。ワッツの作品には、人間を見つめる強靱な力を感じる。自分を見つめるかのように他者を見つめる力。そのまなざしを、学ばなければと思う。